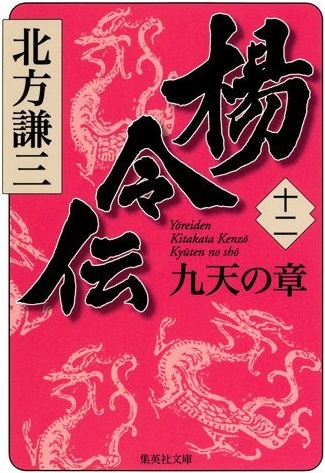
楊令伝 十二
九天の章(きゅうてんのしょう)
金国内での政争を粘罕が制し、漢人を推戴した傀儡国家・斉が中原に建国された。
李富が操る南宋では、趙構が『抗金』の檄を飛ばし、皇太子に窅を用立する。
一方、梁山泊は西域との交易を順調に続け、さらに富を増やし始めていた。
だが、李媛と李英の姉弟が護衛する梁山泊の商隊が、突如、金軍に襲われる。
急襲を知らせるため、王定六は梁山泊へ向けて疾風の如く駆け抜ける。
楊令伝、火急の第十二巻。
九天の章 目次
天損の夢
地周の光
天貴の夢
天満の夢
地暗の光
九天の章(きゅうてんのしょう)
金国内での政争を粘罕が制し、漢人を推戴した傀儡国家・斉が中原に建国された。
李富が操る南宋では、趙構が『抗金』の檄を飛ばし、皇太子に窅を用立する。
一方、梁山泊は西域との交易を順調に続け、さらに富を増やし始めていた。
だが、李媛と李英の姉弟が護衛する梁山泊の商隊が、突如、金軍に襲われる。
急襲を知らせるため、王定六は梁山泊へ向けて疾風の如く駆け抜ける。
楊令伝、火急の第十二巻。
九天の章 目次
天損の夢
地周の光
天貴の夢
天満の夢
地暗の光
天損の夢
東への道で、危険を感じることは、ほとんどなかった。
広大な、砂漠である。
砂と、湧水のある場所と、河の流域に集落があるだけだった。
河は、砂漠の中で、次第に細くなり、消えていく。
山なみの雪解けの水が、流れこんでいるのだ。
砂漠に、雨は降らない。
東へは、砂漠の南側の道を通った。
西へ行く時は、北側の道を通ったのだ。
集落が、危険だと感じたことはない。
なにもない、小石と砂の荒野に、数十人が集まっていたりする。
そういう連中が、場合によっては野盗となったりするのだろう、と張横は思った。
それも、ずいぶん減ったのだという。
連れている部下は十数名だが、荷車があるわけではなく、食糧を積んだ馬が三頭いるだけだから、襲う価値もないと見られているのかもしれない。
砂漠一帯の部族を、耶律大石はほぼまとめあげていた。
まだ国というかたちをとっているわけではないが、耶律大石を頂点とした国ができたとしても、なんの不思議もなかった。
ただ、農耕はあまりなされていない。
遊牧の民が、ほとんどだった。
この砂漠に、生きものがいるのか、と最初に入った時、張横は思った。
しかし、人がいた。
羊もいた。
そして、野生の鹿の群れや、背に二つの瘤を持つ駱駝などもいたのだ。
砂と石くれにしか見えない砂漠にも、探すと草があった。
河や泉の近辺には、灌木の茂みが拡がっていたし、湖を中心として、緑に包まれている地帯もあった。
それにしても、広い。
人の手に負えないような広さだと感じられ、それで覇権を求める人間なども現れなかったのだ、と思った。
耶律大石も、覇権を求めているわけではない。
砂漠の北と南に通る、二本の道の安全を求めているだけだ。
それは砂漠全域に眼を光らせていることにもなり、自然に、部族の長たちの上に立つ、という格好になったようだ。
もともと砂漠の東の端に拠点を置いていたが、いまは中央に移り、虎思斡耳朶という大きな集落を作り上げている。
国が建てられれば、そこが都ということになるだろう。
面会した耶律大石は、偉丈夫だったが、尊大な雰囲気など、まるでなかった。
白髪で、髭も白くなっていた。
眼は好奇心に満ちていて、張横が作ろうとしている通信網に、強い関心を示した。
伝令の重要さについては、しっかりとした認識を持っていたが、恒常的な通信網は目新しいことのようだった。
広大なこの地方の通信網の中心は、虎思斡耳朶ということになるので、張横は細かくそれを説明した。
耶律大石は、部下の二人に、それを詳しく書きとらせたいた。
道の各所には、すでに要因は配置してある。
その動きに無理が出ないかどうか、実際に見るのが張横の仕事だった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
東への道で、危険を感じることは、ほとんどなかった。
広大な、砂漠である。
砂と、湧水のある場所と、河の流域に集落があるだけだった。
河は、砂漠の中で、次第に細くなり、消えていく。
山なみの雪解けの水が、流れこんでいるのだ。
砂漠に、雨は降らない。
東へは、砂漠の南側の道を通った。
西へ行く時は、北側の道を通ったのだ。
集落が、危険だと感じたことはない。
なにもない、小石と砂の荒野に、数十人が集まっていたりする。
そういう連中が、場合によっては野盗となったりするのだろう、と張横は思った。
それも、ずいぶん減ったのだという。
連れている部下は十数名だが、荷車があるわけではなく、食糧を積んだ馬が三頭いるだけだから、襲う価値もないと見られているのかもしれない。
砂漠一帯の部族を、耶律大石はほぼまとめあげていた。
まだ国というかたちをとっているわけではないが、耶律大石を頂点とした国ができたとしても、なんの不思議もなかった。
ただ、農耕はあまりなされていない。
遊牧の民が、ほとんどだった。
この砂漠に、生きものがいるのか、と最初に入った時、張横は思った。
しかし、人がいた。
羊もいた。
そして、野生の鹿の群れや、背に二つの瘤を持つ駱駝などもいたのだ。
砂と石くれにしか見えない砂漠にも、探すと草があった。
河や泉の近辺には、灌木の茂みが拡がっていたし、湖を中心として、緑に包まれている地帯もあった。
それにしても、広い。
人の手に負えないような広さだと感じられ、それで覇権を求める人間なども現れなかったのだ、と思った。
耶律大石も、覇権を求めているわけではない。
砂漠の北と南に通る、二本の道の安全を求めているだけだ。
それは砂漠全域に眼を光らせていることにもなり、自然に、部族の長たちの上に立つ、という格好になったようだ。
もともと砂漠の東の端に拠点を置いていたが、いまは中央に移り、虎思斡耳朶という大きな集落を作り上げている。
国が建てられれば、そこが都ということになるだろう。
面会した耶律大石は、偉丈夫だったが、尊大な雰囲気など、まるでなかった。
白髪で、髭も白くなっていた。
眼は好奇心に満ちていて、張横が作ろうとしている通信網に、強い関心を示した。
伝令の重要さについては、しっかりとした認識を持っていたが、恒常的な通信網は目新しいことのようだった。
広大なこの地方の通信網の中心は、虎思斡耳朶ということになるので、張横は細かくそれを説明した。
耶律大石は、部下の二人に、それを詳しく書きとらせたいた。
道の各所には、すでに要因は配置してある。
その動きに無理が出ないかどうか、実際に見るのが張横の仕事だった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
