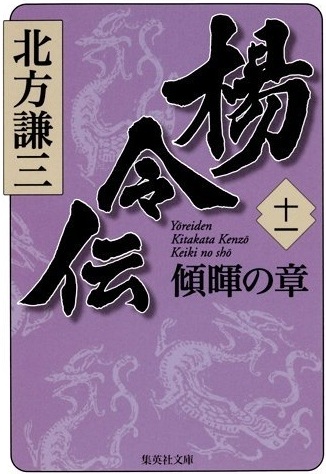
楊令伝 十一
傾暉の章(けいきのしょう)
梁山泊は、国としてのかたちを整えていく。
西域への交易路開拓のため、韓成は西夏に遣わされる。
楊令自ら護衛する最初の商隊が、西域へと出発した。
兀朮らが率いる金軍は、南宋の帝となった趙構を討つために旧宋領への侵攻を続ける。
劉光世は趙構を守って江南を転戦するが、一方で、岳飛と張俊は趙構の招集に応じることなく、それぞれが独立勢力として中原に立っていた。
楊令伝、乱世の第十一巻。
傾暉の章 目次
地光の光
地闊の光
天暴の夢
地微の光
天異の夢
傾暉の章(けいきのしょう)
梁山泊は、国としてのかたちを整えていく。
西域への交易路開拓のため、韓成は西夏に遣わされる。
楊令自ら護衛する最初の商隊が、西域へと出発した。
兀朮らが率いる金軍は、南宋の帝となった趙構を討つために旧宋領への侵攻を続ける。
劉光世は趙構を守って江南を転戦するが、一方で、岳飛と張俊は趙構の招集に応じることなく、それぞれが独立勢力として中原に立っていた。
楊令伝、乱世の第十一巻。
傾暉の章 目次
地光の光
地闊の光
天暴の夢
地微の光
天異の夢
地光の夢
中興府の複雑さは、はじめ韓成が考えたものとは、まるで違っていた。
というより、はじめに考えたのは、賢臣に守られた小国で、豊かではないが、乱れのない国、というものだった。
中興府を外側から見たかぎり、そう思えてしまう。
しかし、一旦内側を覗くと、かなり微妙な均衡の上に、この国が立っているのだということがわかる。
西七百里に、西涼府があった。
そこにいるのは李桂参で、帝の兄に当たる。
面倒なのは、李桂参がもともと皇太子になるはずで、そういう教育も受けてきたことだ。
しかし幼いころから躰が弱く、十五歳までは生きられないだろう、と言われていた。
前の帝は、迷った末に、健勝であった弟の乾順を皇太子にしたのだという。
しかし李桂参は、十五歳になっても死なず、成人するに従って、むしろ頑健にさえなっていった。
李乾順が即位した三十年ほど前には、軍の統轄者の立場を望んだのだという。
軍の統轄は帝がなすことだと、先帝の廷臣たちは拒んだが、それ以上のことをしなかった。
それで李桂参は、あたかも新帝の後見のごとき立場をとりはじめた。
若い廷臣たちが手を組んで、李桂参を排除する、という事件が起きたようだ。
それで李桂参は西涼府へ移り、そこから動かなくなったのだという。
朝廷内に、勢力を扶植することは、忘れなかった。
当然の成行きで、不平を抱いた廷臣が、西涼府に心を寄せるようになっている。
朝廷に出入りする間に、韓成はそういうことを知っていった。
いまは、梁山泊の交易の道が、西涼府に眼をつけられている。
その道が、西夏に富をもたらすことになれば、今の廷臣たちの力がさらに強くなるからだ。
秦容と郤妁も、そのことを理解した。
韓成が、朝廷に行くまでの間、護衛するのが二人の役目である。
中興府に留まったままの、公孫勝や戴宋の動きは、あまり気にしないようにした。
与えられた屋敷のひと部屋に、いることも少ないのだ。
「たえず、見張られていたのですね、韓成殿は」
屋敷から宮殿まで、しばらく歩かなければならない。
その間は、たえず見張られているということになる。
「これまで、ひとりで歩いていたのだ、秦容。なにも、起こらなかった」
「なにか起きてからでは、遅いのでしょう?」
「確かにな」
交易の道を通すことに、韓成は徐々に情熱を感じはじめていた。
ここよりさらに西の、広大な砂漠を通ってきた物資が、梁山泊に運び込まれ、それがさらに東の日本まで運ばれる。
日本からの物資も、西域まで運ばれる。
古来、そこに物資が通る道があり、いまも商人たちが往来していることは、知っている。
しかし、国としてそれがなされたことは、数少ない。
梁山泊が、国としてそれをなす。
そのことにどういう意味があるかではなく、できるかどうかだった。
聚義庁で計画している量の物資が動けば、充分に国庫を満たすだけのものはあるはずだ。
西夏より西は、武松が担当することになったが、はじめの話を耶律大石としてきたのは、杜興だった。
韓成自身は、まだ耶律大石と会ったことはない。
(…この続きは本書にてどうぞ)
中興府の複雑さは、はじめ韓成が考えたものとは、まるで違っていた。
というより、はじめに考えたのは、賢臣に守られた小国で、豊かではないが、乱れのない国、というものだった。
中興府を外側から見たかぎり、そう思えてしまう。
しかし、一旦内側を覗くと、かなり微妙な均衡の上に、この国が立っているのだということがわかる。
西七百里に、西涼府があった。
そこにいるのは李桂参で、帝の兄に当たる。
面倒なのは、李桂参がもともと皇太子になるはずで、そういう教育も受けてきたことだ。
しかし幼いころから躰が弱く、十五歳までは生きられないだろう、と言われていた。
前の帝は、迷った末に、健勝であった弟の乾順を皇太子にしたのだという。
しかし李桂参は、十五歳になっても死なず、成人するに従って、むしろ頑健にさえなっていった。
李乾順が即位した三十年ほど前には、軍の統轄者の立場を望んだのだという。
軍の統轄は帝がなすことだと、先帝の廷臣たちは拒んだが、それ以上のことをしなかった。
それで李桂参は、あたかも新帝の後見のごとき立場をとりはじめた。
若い廷臣たちが手を組んで、李桂参を排除する、という事件が起きたようだ。
それで李桂参は西涼府へ移り、そこから動かなくなったのだという。
朝廷内に、勢力を扶植することは、忘れなかった。
当然の成行きで、不平を抱いた廷臣が、西涼府に心を寄せるようになっている。
朝廷に出入りする間に、韓成はそういうことを知っていった。
いまは、梁山泊の交易の道が、西涼府に眼をつけられている。
その道が、西夏に富をもたらすことになれば、今の廷臣たちの力がさらに強くなるからだ。
秦容と郤妁も、そのことを理解した。
韓成が、朝廷に行くまでの間、護衛するのが二人の役目である。
中興府に留まったままの、公孫勝や戴宋の動きは、あまり気にしないようにした。
与えられた屋敷のひと部屋に、いることも少ないのだ。
「たえず、見張られていたのですね、韓成殿は」
屋敷から宮殿まで、しばらく歩かなければならない。
その間は、たえず見張られているということになる。
「これまで、ひとりで歩いていたのだ、秦容。なにも、起こらなかった」
「なにか起きてからでは、遅いのでしょう?」
「確かにな」
交易の道を通すことに、韓成は徐々に情熱を感じはじめていた。
ここよりさらに西の、広大な砂漠を通ってきた物資が、梁山泊に運び込まれ、それがさらに東の日本まで運ばれる。
日本からの物資も、西域まで運ばれる。
古来、そこに物資が通る道があり、いまも商人たちが往来していることは、知っている。
しかし、国としてそれがなされたことは、数少ない。
梁山泊が、国としてそれをなす。
そのことにどういう意味があるかではなく、できるかどうかだった。
聚義庁で計画している量の物資が動けば、充分に国庫を満たすだけのものはあるはずだ。
西夏より西は、武松が担当することになったが、はじめの話を耶律大石としてきたのは、杜興だった。
韓成自身は、まだ耶律大石と会ったことはない。
(…この続きは本書にてどうぞ)
