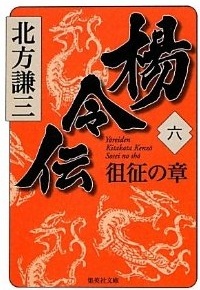
楊令伝 六
徂征の章(そせいのしょう)
南北の動乱が終結し、呉用は江南から救出された。
金国では阿骨打亡き後に呉乞買が即位し、国の体制を整えつつある。
梁山泊は、制圧した地域を守りながら、来るべき宗金軍との全面対決に向けて戦力を蓄えていた。
侯真は、黒騎兵を抜けて新たな任務に就く。
一方、扈三娘は息子たちが消えたという報せを受けて洞宮山へ駆けつけるが、聞燗章の劣情渦巻く奸計に陥ってしまう。
楊令伝、風雲の第6巻。
徂征の章 目次
地空の光
天哭の夢
地蔵の光
地弧の光
地英の光
徂征の章(そせいのしょう)
南北の動乱が終結し、呉用は江南から救出された。
金国では阿骨打亡き後に呉乞買が即位し、国の体制を整えつつある。
梁山泊は、制圧した地域を守りながら、来るべき宗金軍との全面対決に向けて戦力を蓄えていた。
侯真は、黒騎兵を抜けて新たな任務に就く。
一方、扈三娘は息子たちが消えたという報せを受けて洞宮山へ駆けつけるが、聞燗章の劣情渦巻く奸計に陥ってしまう。
楊令伝、風雲の第6巻。
徂征の章 目次
地空の光
天哭の夢
地蔵の光
地弧の光
地英の光
地空の光
いつもより、雪が早かった。
年が明けるころには、会寧府の近辺は雪に覆われていた。
外の竃で火を燃やす。
それは床の下を伝わり、壁の中を這い上がり、煙を外に逃がすようになっている。
床が暖かいので、家の中の寒さは、それほどでもない。
この季節になると、誰もが毛皮の帽子を被る。
蔡福も、金国の民にならって、鼬の皮の帽子を被っていた。
それだけで、感じる寒さはだいぶ違うのだ。
ほぼ、毎日宮殿に出仕した。
粘罕と。さまざまなことについて、決めていかなければならないのだ。
呉乞買は、帝位に即いてからは、完顔晟と名乗り、それなりにやるべきことをこなしていた。
その気になれば、あるところまでは、できる男だ。
ただ、阿骨打のように、慕われてはいない。
どこかに、計算高いところが覗いてしまうのだ。
会寧府には、各地から人が集まりはじめていた。
人が集まれば、物も集まる。
会寧府は、ようやく金国の都という姿を整えつつあった。
蔡福が毎日出仕するのは、家にいたくなかったからでもあった。
馬嫖のところにいても、真婉は気づいて悋気を起こす。
何度か、無理に家に入ってこようとした。
そのたびに、馬嫖は竦みあがる。
いま、馬嫖のための家を、別のところに用意しているところだった。
真婉と馬嫖を、隣り合わせて住まわせようとしたのは、真婉に気を遣ったからだ。
家の大きさから、使用人の数まで、すべて真婉を超えないようにした。
そういう気遣いも、いまの真婉には通じはしなかった。
馬嫖を見る眼はともかく、祭福を見る時も、全身に殺気を漲らせている。
そういう悋気を起こすようになったのは、蔡福が真婉を抱かなくなったからだ。
抱かれる愉悦の中で、真婉はなんとか自分を見失わないで済んだのかも知れない。
蔡福が、真碗の不思議ななまめかしさに魅かれていたのは、間違いないことだ。
なんでもない女たっだら、とうに叩き出していると思うほど、蔡福は嫌われた。
死んだ弟の妻を、妻にする。
女真族のその習慣を、それほどためらわずに受け入れたのは、どこかで真碗に魅かれていたからだろう。
それが、独特のなまめかしさだとわかったのは、かなり時が経ってからだった。
昼間でも、抱かれたい時は、賢い母の顔を装いながらも眼には怪しい火が燃えていて、いても立ってもいられない様な気分に、蔡福をさせたものだった。
真碗に対してまだ未練があるとしたら、それには交合の快感がどこかにまとまりついている。
馬嫖は、気立てがよく、きれいな女だったが、閨房ではありふれた仕草しかしなかった。
帰宅するのは、夜が更けてからである。
真碗は、大抵寝ていて、迎えるのは、蔡福の世話が仕事の、使用人の老婆である。
「おかえりなさいませ」
家の入口で、套衣についた雪を払っていると、真碗の声が迎えたので、蔡福は一瞬躰を硬くした。
「ああ」
蔡福は、うつむいたまま、真碗と眼を合わせずに家に入った。
(…この続きは本書にてどうぞ)
いつもより、雪が早かった。
年が明けるころには、会寧府の近辺は雪に覆われていた。
外の竃で火を燃やす。
それは床の下を伝わり、壁の中を這い上がり、煙を外に逃がすようになっている。
床が暖かいので、家の中の寒さは、それほどでもない。
この季節になると、誰もが毛皮の帽子を被る。
蔡福も、金国の民にならって、鼬の皮の帽子を被っていた。
それだけで、感じる寒さはだいぶ違うのだ。
ほぼ、毎日宮殿に出仕した。
粘罕と。さまざまなことについて、決めていかなければならないのだ。
呉乞買は、帝位に即いてからは、完顔晟と名乗り、それなりにやるべきことをこなしていた。
その気になれば、あるところまでは、できる男だ。
ただ、阿骨打のように、慕われてはいない。
どこかに、計算高いところが覗いてしまうのだ。
会寧府には、各地から人が集まりはじめていた。
人が集まれば、物も集まる。
会寧府は、ようやく金国の都という姿を整えつつあった。
蔡福が毎日出仕するのは、家にいたくなかったからでもあった。
馬嫖のところにいても、真婉は気づいて悋気を起こす。
何度か、無理に家に入ってこようとした。
そのたびに、馬嫖は竦みあがる。
いま、馬嫖のための家を、別のところに用意しているところだった。
真婉と馬嫖を、隣り合わせて住まわせようとしたのは、真婉に気を遣ったからだ。
家の大きさから、使用人の数まで、すべて真婉を超えないようにした。
そういう気遣いも、いまの真婉には通じはしなかった。
馬嫖を見る眼はともかく、祭福を見る時も、全身に殺気を漲らせている。
そういう悋気を起こすようになったのは、蔡福が真婉を抱かなくなったからだ。
抱かれる愉悦の中で、真婉はなんとか自分を見失わないで済んだのかも知れない。
蔡福が、真碗の不思議ななまめかしさに魅かれていたのは、間違いないことだ。
なんでもない女たっだら、とうに叩き出していると思うほど、蔡福は嫌われた。
死んだ弟の妻を、妻にする。
女真族のその習慣を、それほどためらわずに受け入れたのは、どこかで真碗に魅かれていたからだろう。
それが、独特のなまめかしさだとわかったのは、かなり時が経ってからだった。
昼間でも、抱かれたい時は、賢い母の顔を装いながらも眼には怪しい火が燃えていて、いても立ってもいられない様な気分に、蔡福をさせたものだった。
真碗に対してまだ未練があるとしたら、それには交合の快感がどこかにまとまりついている。
馬嫖は、気立てがよく、きれいな女だったが、閨房ではありふれた仕草しかしなかった。
帰宅するのは、夜が更けてからである。
真碗は、大抵寝ていて、迎えるのは、蔡福の世話が仕事の、使用人の老婆である。
「おかえりなさいませ」
家の入口で、套衣についた雪を払っていると、真碗の声が迎えたので、蔡福は一瞬躰を硬くした。
「ああ」
蔡福は、うつむいたまま、真碗と眼を合わせずに家に入った。
(…この続きは本書にてどうぞ)
