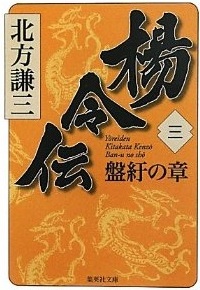
楊令伝 三
盤紆の章(ばんうのしょう)
楊令は、幻王として金軍を率いながら、
梁山泊の重装備部隊とも連携し、遼に侵攻した
呉用が潜入する江南では方臘の反乱が拡大し、
宋地方軍に大きな痛手を与えている。
一方で聞燠章は、帝の悲願の地である燕雲十六州に、ある野望を抱いていた。
ついに宋禁軍に出動の勅命が下り、童貫は岳飛を伴い江南へ出陣する。
宋、遼、金国、方臘と入り乱れての闘いの火蓋が切られた。
楊令伝、擾乱の第三巻。
辺烽の章 目次
天富の夢
地賊の光
地佐の光
地醜の光
地魁の光
盤紆の章(ばんうのしょう)
楊令は、幻王として金軍を率いながら、
梁山泊の重装備部隊とも連携し、遼に侵攻した
呉用が潜入する江南では方臘の反乱が拡大し、
宋地方軍に大きな痛手を与えている。
一方で聞燠章は、帝の悲願の地である燕雲十六州に、ある野望を抱いていた。
ついに宋禁軍に出動の勅命が下り、童貫は岳飛を伴い江南へ出陣する。
宋、遼、金国、方臘と入り乱れての闘いの火蓋が切られた。
楊令伝、擾乱の第三巻。
辺烽の章 目次
天富の夢
地賊の光
地佐の光
地醜の光
地魁の光
天富の夢
二百名の兵は、よく働いた。
もともとの李応の部下は五十名だけだが、四名を最小の隊にし、経験のない者三名と組ませた。
重装備を作るための経験は、戦とはまるで違うところにあるらしい。
梁山泊に加わってすぐに、杜興は李応と離された。
だから、李応の重装備の制作には、関係のないところにいたのだ。
細かいことの監督など、やれるわけがなかった。
兵たちが躰を動かしているかどうか、眼を光らせているだけだ。
重装備を制作するには二百名で足りるが、それを運び、実践で遣うには、人数が足りなかった。
そのための一千の部隊が、そのうち到着すると言って、郝瑾は去っていった。
人数が揃ったら、それを遣うための訓練をしなければならない。
それにもやはり、五十名の経験者が必要なのだろう。
自分の仕事は、重装備部隊をまとめることだった。
李媛が隊長で、たとえ若い女であろうと、李媛を頂点とした命令系統は、しっかり作りあげなければならないのだ。
まず二百名について、杜興は徹底した命令系統を作ろうとした。
しかし、うまくいかない。逆らう者が、少なくないのだ。
なぜ逆らわられるのか、杜興はすぐに気付いた。
本気になっているからだ。
細かいところまで、眼を配りすぎるからだ。
いい加減になろうとした。
適当に、悪態だけついていようと思った。
しかし、どうしても細かいところにまで、眼がいってしまう。
李応に対してできなかったことを、李媛のためにしてやりたい、という気持ちが強すぎるからだ。
それも、わかっていた。
このままだと、和を乱すのが自分ということになりかねない、と杜興は思った。
いっそのこと、昼寝でも決めこんでしまえばいいのだが、それも落ち着かなかった。
二万余の部隊が、阿勒楚喀から南下してきた。
指揮をしているのは、唐昇とかいうかつて北京大名府の将軍だった男で、軍師に許貫忠がついていた。
「一千の部隊を、ここに残していくことになっているのだがな、杜興」
「本隊は?」
「本隊というわけではなく、一千はここまで連れてきたというだけのことだ」
つまり、その一千が重装備の部隊、ということになるのだろう。
「調練はしてあるのか、唐昇?」
「重装備を扱う調練は、していない。
普通の歩兵だが、粘り強い者を選んである。
重装備に関しては、ここでしっかり叩き込んで貰うしかない」
「わかった。しかし、調練の指揮をする者がおらんのう」
「おまえだ、杜興」
「わしは、重装備の扱いは知らんよ」
「誰も知らない。
作った者がやるのが一番だが、それだけの時はなさそうだ」
「おまえは?」
「出動態勢のまま、国境で待機する」
「率いているのは金軍であって、梁山泊軍ではないのだな」
「そうだ。陛下の軍だ。
ただ、あの一千だけは、幻王の軍であり、全員が漢名を持っている。
幻王の軍はみんなそうで、いまは黄竜府の近郊に展開していて、一万に達する」
「半分は、歩兵か」
郝瑾が率いている二千のうちの半分は、歩兵だった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
二百名の兵は、よく働いた。
もともとの李応の部下は五十名だけだが、四名を最小の隊にし、経験のない者三名と組ませた。
重装備を作るための経験は、戦とはまるで違うところにあるらしい。
梁山泊に加わってすぐに、杜興は李応と離された。
だから、李応の重装備の制作には、関係のないところにいたのだ。
細かいことの監督など、やれるわけがなかった。
兵たちが躰を動かしているかどうか、眼を光らせているだけだ。
重装備を制作するには二百名で足りるが、それを運び、実践で遣うには、人数が足りなかった。
そのための一千の部隊が、そのうち到着すると言って、郝瑾は去っていった。
人数が揃ったら、それを遣うための訓練をしなければならない。
それにもやはり、五十名の経験者が必要なのだろう。
自分の仕事は、重装備部隊をまとめることだった。
李媛が隊長で、たとえ若い女であろうと、李媛を頂点とした命令系統は、しっかり作りあげなければならないのだ。
まず二百名について、杜興は徹底した命令系統を作ろうとした。
しかし、うまくいかない。逆らう者が、少なくないのだ。
なぜ逆らわられるのか、杜興はすぐに気付いた。
本気になっているからだ。
細かいところまで、眼を配りすぎるからだ。
いい加減になろうとした。
適当に、悪態だけついていようと思った。
しかし、どうしても細かいところにまで、眼がいってしまう。
李応に対してできなかったことを、李媛のためにしてやりたい、という気持ちが強すぎるからだ。
それも、わかっていた。
このままだと、和を乱すのが自分ということになりかねない、と杜興は思った。
いっそのこと、昼寝でも決めこんでしまえばいいのだが、それも落ち着かなかった。
二万余の部隊が、阿勒楚喀から南下してきた。
指揮をしているのは、唐昇とかいうかつて北京大名府の将軍だった男で、軍師に許貫忠がついていた。
「一千の部隊を、ここに残していくことになっているのだがな、杜興」
「本隊は?」
「本隊というわけではなく、一千はここまで連れてきたというだけのことだ」
つまり、その一千が重装備の部隊、ということになるのだろう。
「調練はしてあるのか、唐昇?」
「重装備を扱う調練は、していない。
普通の歩兵だが、粘り強い者を選んである。
重装備に関しては、ここでしっかり叩き込んで貰うしかない」
「わかった。しかし、調練の指揮をする者がおらんのう」
「おまえだ、杜興」
「わしは、重装備の扱いは知らんよ」
「誰も知らない。
作った者がやるのが一番だが、それだけの時はなさそうだ」
「おまえは?」
「出動態勢のまま、国境で待機する」
「率いているのは金軍であって、梁山泊軍ではないのだな」
「そうだ。陛下の軍だ。
ただ、あの一千だけは、幻王の軍であり、全員が漢名を持っている。
幻王の軍はみんなそうで、いまは黄竜府の近郊に展開していて、一万に達する」
「半分は、歩兵か」
郝瑾が率いている二千のうちの半分は、歩兵だった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
