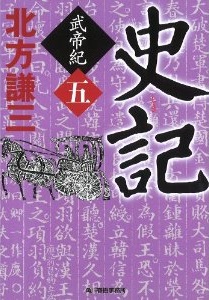
史記 武帝紀 5
前漢の中国。
大きな戦果をあげてきた大将軍・衛青を喪った漢軍は、新たな単于の下で勢いに乗る匈奴に反攻を許す。
今や匈奴軍の要となった頭屠の活躍により、漢の主力部隊である李広利軍三万はあえなく潰走した。
一方、わずか五千の歩兵を率いて匈奴の精鋭部隊が持つ地に向かい、善戦する李陵。
匈奴の地で囚われの身となり、独り北辺の地に生きる蘇武。
そして司馬遷は、悲憤を超え、時代に流されようとする運命を冷徹な筆でつづり続ける―――。
目次
味旦
離憂
硬咽の地
抗殺の時
孤負の砂
前漢の中国。
大きな戦果をあげてきた大将軍・衛青を喪った漢軍は、新たな単于の下で勢いに乗る匈奴に反攻を許す。
今や匈奴軍の要となった頭屠の活躍により、漢の主力部隊である李広利軍三万はあえなく潰走した。
一方、わずか五千の歩兵を率いて匈奴の精鋭部隊が持つ地に向かい、善戦する李陵。
匈奴の地で囚われの身となり、独り北辺の地に生きる蘇武。
そして司馬遷は、悲憤を超え、時代に流されようとする運命を冷徹な筆でつづり続ける―――。
目次
味旦
離憂
硬咽の地
抗殺の時
孤負の砂
味旦
李陵が、本陣への報告で長安に戻っていた時、蘇武の母が死んだ。
蘇武は、信節を奉持し、匈奴に使いしていて留守だった。
代わりにはならないものの、せめてもの思いを抱いて、李陵は蘇武の母を送った。
蘇武が、匈奴に地で囚われていたという噂を聞いたのは、張掖に戻ってからで、長安にはこれから知らせが行くようだった。
使節が、そのまま囚われてしまうことは、めずらしくなかった。
漢と匈奴は、お互いにたえずそれをやり、なにかあると交換するということを、くり返している。
匈奴の単干の且鞮侯は、南へ下りてきた単干庭を守り抜くだけでなく、漢に攻撃を加えるという態度を、まったく崩そうとしなかった。
漢と匈奴は、かつてのような、戦の状態になっていた。
張掖でも、匈奴の軍を見かけたら、ためらうことなく討て、という通達が届いていた。
匈奴の軍は、しばしば見かけた。
しかし討とうにも、馬がなかった。
歩兵で騎馬隊を追うことはできず、通達そのものが、意味のないことのように、李陵には思えた。
長安では、匈奴討伐の準備が進められているという。
総指揮官は、大宛遠征で功績をあげた、李広利将軍である。
軍には、衛青代将軍も、霍去病将軍もいなかった。
李広利将軍の指揮に、李陵は大きな疑問を抱いていたが、口に出せることではなかった。
五千もの、部下がいる。
しかしそのすべてが歩兵で、守りの戦しか方法はなかった。
祖父は、守りに関しては、衛青代将軍が公然と認めたほどの、名将だった。
祖父に教えられた陣形など、李陵の頭にしっかり入っていて、さらなる工夫を重ねていた。
しかし、匈奴が攻めてくるということはなかった。
守りが堅いと見ると、別の場所を攻撃するのだ。
以前に率いていたあの八百騎がいたら、ち李陵はしばしば考えた。
そうすれば、五千の歩兵も、その数以上の生かし方ができる。
長安には何度も願いを出していたが、騎馬隊は侵攻の激しい場所に置くという発想しか、本営にはなかった。
張掖に八百騎がいるだけで、匈奴の動きにかなり制約を与えることが出来る、ということを、誰も理解してくれないのだ。
匈奴に囲われの身になっている蘇武のことは、しばしば考えた。
蘇武の性格は、降伏を肯んずるものではない。
命を捨ててでも、使節としての名分は守ろうとするだろう。
忠義の心が強いとも言えたし、頑迷固陋という一面が、ないわけでもなかった。
囲われ続けているのだから、つらい思いの中にいるに違いないことは、容易に想像できた。
救うには、匈奴の小王のひとりか二人を捕え、交換することだ。
そのためにも、やはり騎馬隊が必要だった。
歩兵は、鍛えるだけ鍛えあげている。
弓矢に関しては、一斉に同じ距離を飛ばすことができる。
一千ずつ交互斉射も、わずかの間でやってのけるので、のべつ相手に矢の雨を降らせることもできる。
剣や戟に関しては、同数ならば、漢軍のどの部隊にも負けない自信があった。
それだけでなく、移動の速さ、その距離、土塁の築き方なども、どこにも負けない自信が、李陵にはあった。
李陵の軍については、匈奴の方がその力をよく知っていて、近づいてくることをしない。
周囲の将軍たちは、李陵の軍の実力を知っていても、それを長安に報告することはしなかった。
せいぜい、自分たちの代りに闘わせようとするくらいだ。
闘う機会があれば、李陵は必ず前線へ出ていった。
闘うたびに、兵たちが強くなるのが、はっきり感じられるからだ。
(…この続きは本書にてどうぞ)
李陵が、本陣への報告で長安に戻っていた時、蘇武の母が死んだ。
蘇武は、信節を奉持し、匈奴に使いしていて留守だった。
代わりにはならないものの、せめてもの思いを抱いて、李陵は蘇武の母を送った。
蘇武が、匈奴に地で囚われていたという噂を聞いたのは、張掖に戻ってからで、長安にはこれから知らせが行くようだった。
使節が、そのまま囚われてしまうことは、めずらしくなかった。
漢と匈奴は、お互いにたえずそれをやり、なにかあると交換するということを、くり返している。
匈奴の単干の且鞮侯は、南へ下りてきた単干庭を守り抜くだけでなく、漢に攻撃を加えるという態度を、まったく崩そうとしなかった。
漢と匈奴は、かつてのような、戦の状態になっていた。
張掖でも、匈奴の軍を見かけたら、ためらうことなく討て、という通達が届いていた。
匈奴の軍は、しばしば見かけた。
しかし討とうにも、馬がなかった。
歩兵で騎馬隊を追うことはできず、通達そのものが、意味のないことのように、李陵には思えた。
長安では、匈奴討伐の準備が進められているという。
総指揮官は、大宛遠征で功績をあげた、李広利将軍である。
軍には、衛青代将軍も、霍去病将軍もいなかった。
李広利将軍の指揮に、李陵は大きな疑問を抱いていたが、口に出せることではなかった。
五千もの、部下がいる。
しかしそのすべてが歩兵で、守りの戦しか方法はなかった。
祖父は、守りに関しては、衛青代将軍が公然と認めたほどの、名将だった。
祖父に教えられた陣形など、李陵の頭にしっかり入っていて、さらなる工夫を重ねていた。
しかし、匈奴が攻めてくるということはなかった。
守りが堅いと見ると、別の場所を攻撃するのだ。
以前に率いていたあの八百騎がいたら、ち李陵はしばしば考えた。
そうすれば、五千の歩兵も、その数以上の生かし方ができる。
長安には何度も願いを出していたが、騎馬隊は侵攻の激しい場所に置くという発想しか、本営にはなかった。
張掖に八百騎がいるだけで、匈奴の動きにかなり制約を与えることが出来る、ということを、誰も理解してくれないのだ。
匈奴に囲われの身になっている蘇武のことは、しばしば考えた。
蘇武の性格は、降伏を肯んずるものではない。
命を捨ててでも、使節としての名分は守ろうとするだろう。
忠義の心が強いとも言えたし、頑迷固陋という一面が、ないわけでもなかった。
囲われ続けているのだから、つらい思いの中にいるに違いないことは、容易に想像できた。
救うには、匈奴の小王のひとりか二人を捕え、交換することだ。
そのためにも、やはり騎馬隊が必要だった。
歩兵は、鍛えるだけ鍛えあげている。
弓矢に関しては、一斉に同じ距離を飛ばすことができる。
一千ずつ交互斉射も、わずかの間でやってのけるので、のべつ相手に矢の雨を降らせることもできる。
剣や戟に関しては、同数ならば、漢軍のどの部隊にも負けない自信があった。
それだけでなく、移動の速さ、その距離、土塁の築き方なども、どこにも負けない自信が、李陵にはあった。
李陵の軍については、匈奴の方がその力をよく知っていて、近づいてくることをしない。
周囲の将軍たちは、李陵の軍の実力を知っていても、それを長安に報告することはしなかった。
せいぜい、自分たちの代りに闘わせようとするくらいだ。
闘う機会があれば、李陵は必ず前線へ出ていった。
闘うたびに、兵たちが強くなるのが、はっきり感じられるからだ。
(…この続きは本書にてどうぞ)
