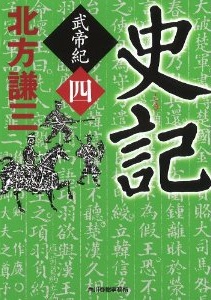
史記 武帝紀 4
前漢の中国。
匈奴より河南を奪還し、さらに西域へ勢力を伸ばそうと目論む武帝・劉徹は、その矢先に霍去病を病で失う。
喪失感から、心に闇を抱える劉徹。
一方、そんな天子の下、若き才が芽吹く。
泰山封禅に参列できず憤死した父の遺志を継ぐ司馬遷。
名将・李広の孫にして、大将軍の衛青がその才を認めるほどの逞しい成長を見せる李陵。
そして、李陵の友・蘇武は文官となり、劉徹より賜りし短剣を胸に匈奴へ向かう――。
目次
八裔
泰山封禅
情緬の日々
首丘
霑赤の汗
前漢の中国。
匈奴より河南を奪還し、さらに西域へ勢力を伸ばそうと目論む武帝・劉徹は、その矢先に霍去病を病で失う。
喪失感から、心に闇を抱える劉徹。
一方、そんな天子の下、若き才が芽吹く。
泰山封禅に参列できず憤死した父の遺志を継ぐ司馬遷。
名将・李広の孫にして、大将軍の衛青がその才を認めるほどの逞しい成長を見せる李陵。
そして、李陵の友・蘇武は文官となり、劉徹より賜りし短剣を胸に匈奴へ向かう――。
目次
八裔
泰山封禅
情緬の日々
首丘
霑赤の汗
八裔
郎中の仕事は、特に難しいことがあるわけではなかった。
とにかく、人数が多い。
その中の、ひとりに過ぎない。
出仕すると、方々に放置されている、竹簡を整理する仕事をしていることが多かった。
帝の眼にとまることなど、まずないので、やりたがる者はいなかったのだ。
整理するためには、中身を読まなければならず、時々面白いものがあることを、司馬遷は発見したのだった。
洪水の報告があった。
情景が眼に浮かぶような、しっかりとした文章で綴られていた。
これだけの文章が書ける役人が、地方にもいるのだ。
嘆願書の類なども、多く放置されていた。
稚拙だが、心情の溢れた文章だったりする。
放置されている竹簡は、不要なものだけだった。
大事なものは、侍中が眼を通した段階で、丞相府に上げられるか、どこかに保管されるかするのだろう。
稀には、帝が手にとることがあるかもしれない。
不要なものを焼くには、さまざまな手続きを経なければならないようだった。
焼いたあとに、あれが必要だということになったら、焼却を許した者の責任になる。
だから、焼くためにどういう手続きをとればいかは決められていても、実際に焼こうという考えなど、誰も持っていないのだった。
終日、つまらない竹簡の文章を読み続け、内容によって、棚に分ける。
そんな仕事を黙々とやっている司馬遷は、変わり者というふうに、周囲からは見られていた。
邪魔をする者はいない。
これから先、もう誰の眼にも触れることがないであろう竹簡の整理など、まったく出世には繋がらないのだ。
郎中は、官史として出世したい者の、最初の役職でもあった。
司馬遷は、すでに史官でもあった。
昇っていける先は見えていて、太史令がせいぜいだろう。
いま太史令は、父の談であった。
学識を求められはするが、儒家などとはまるで違っていた。
心の底から、語り合える友はいなかった。
道理など、実際は無駄なものだ、と思っている輩が、ほとんどだった。
司馬遷が道理を説くと、うるさそうな顔をされるだけだ。
口を閉じて、ひたすら竹簡の整理をしている。
それは、ほかの郎中たちにとって、都合のいいことなのかもしれない。
巴蜀へ行くことになっていた。
そこへ加えられたのも、行きたいものが少なかったからだ。
司馬遷はそれを望んだわけではなく、いかなる意思も示さなかった。
それで、押しつけられたとも言える。
しかし、出発がいつかは、定かではなかった。
西南夷を討つために、巴蜀に兵が集められていて、それが整うころに、出発ということのようだった。
西南夷との戦は、匈奴との戦と較べて、それほど切迫したものとは見えなかった。
匈奴は手強い相手のようで、漠北に打ち払ったと言っても、その動静にはたえず気を配られていた。
軍を出して、砂漠まで行ってみても、匈奴に出会わなかったことが、一再ではないらしい。
戦のことはよくわからなかった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
郎中の仕事は、特に難しいことがあるわけではなかった。
とにかく、人数が多い。
その中の、ひとりに過ぎない。
出仕すると、方々に放置されている、竹簡を整理する仕事をしていることが多かった。
帝の眼にとまることなど、まずないので、やりたがる者はいなかったのだ。
整理するためには、中身を読まなければならず、時々面白いものがあることを、司馬遷は発見したのだった。
洪水の報告があった。
情景が眼に浮かぶような、しっかりとした文章で綴られていた。
これだけの文章が書ける役人が、地方にもいるのだ。
嘆願書の類なども、多く放置されていた。
稚拙だが、心情の溢れた文章だったりする。
放置されている竹簡は、不要なものだけだった。
大事なものは、侍中が眼を通した段階で、丞相府に上げられるか、どこかに保管されるかするのだろう。
稀には、帝が手にとることがあるかもしれない。
不要なものを焼くには、さまざまな手続きを経なければならないようだった。
焼いたあとに、あれが必要だということになったら、焼却を許した者の責任になる。
だから、焼くためにどういう手続きをとればいかは決められていても、実際に焼こうという考えなど、誰も持っていないのだった。
終日、つまらない竹簡の文章を読み続け、内容によって、棚に分ける。
そんな仕事を黙々とやっている司馬遷は、変わり者というふうに、周囲からは見られていた。
邪魔をする者はいない。
これから先、もう誰の眼にも触れることがないであろう竹簡の整理など、まったく出世には繋がらないのだ。
郎中は、官史として出世したい者の、最初の役職でもあった。
司馬遷は、すでに史官でもあった。
昇っていける先は見えていて、太史令がせいぜいだろう。
いま太史令は、父の談であった。
学識を求められはするが、儒家などとはまるで違っていた。
心の底から、語り合える友はいなかった。
道理など、実際は無駄なものだ、と思っている輩が、ほとんどだった。
司馬遷が道理を説くと、うるさそうな顔をされるだけだ。
口を閉じて、ひたすら竹簡の整理をしている。
それは、ほかの郎中たちにとって、都合のいいことなのかもしれない。
巴蜀へ行くことになっていた。
そこへ加えられたのも、行きたいものが少なかったからだ。
司馬遷はそれを望んだわけではなく、いかなる意思も示さなかった。
それで、押しつけられたとも言える。
しかし、出発がいつかは、定かではなかった。
西南夷を討つために、巴蜀に兵が集められていて、それが整うころに、出発ということのようだった。
西南夷との戦は、匈奴との戦と較べて、それほど切迫したものとは見えなかった。
匈奴は手強い相手のようで、漠北に打ち払ったと言っても、その動静にはたえず気を配られていた。
軍を出して、砂漠まで行ってみても、匈奴に出会わなかったことが、一再ではないらしい。
戦のことはよくわからなかった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
