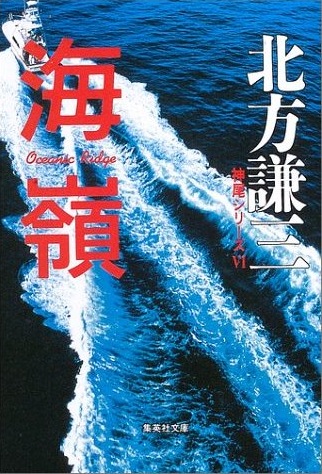
海嶺
神尾シリーズⅥ
両親を亡くしたイタリア少年・マリオと暮らすようになり、恵子とともに彼の「親」となることを決意した神尾。
だがマリオにはシチリア・マフィアの相続問題が絡んでいた。
この決着をつけるべく神尾はマリオを伴い遠くシチリア島へ渡る。
刺客たちに狙われながらも、一族の長老であり、祖父であるステファノと対峙する。
国際ハードボイルドのシリーズ第6弾。
神尾シリーズⅥ
両親を亡くしたイタリア少年・マリオと暮らすようになり、恵子とともに彼の「親」となることを決意した神尾。
だがマリオにはシチリア・マフィアの相続問題が絡んでいた。
この決着をつけるべく神尾はマリオを伴い遠くシチリア島へ渡る。
刺客たちに狙われながらも、一族の長老であり、祖父であるステファノと対峙する。
国際ハードボイルドのシリーズ第6弾。
左を出し、右を突きあげ、もう一発左をフォローした。秋月は尻餅をつき、首を左右に振った。
私は、乱れた息を整えた。
「やめだ、くそっ」
秋月は、明らかに私のボディのあたりを打つのを、遠慮していた。
私はヘッドギアをむしり取ると、リング下にいた長坂に投げた。
「相手をする秋月が、かわいそうだぜ」
リングを降りると、長坂が小声で言った。秋月は顔ばかり狙って打ってくるので、私は自分のブロックとヘッドギアで、まともなパンチは一発も貰わずに済んでいた。
「その躰で、二ラウンドも三ラウンドもスパーができるというのが、まずおかしいんだ」
私の躰は傷だらけで、その傷が二つか三つ増えたというだけのことだった。
腎臓を、ひとつ取った。
誰かに提供したわけではなく、銃弾で破裂させられ、なんの役にも立たないものとして、棄てられたのだ。
もう七カ月も前のことで、私は二週間で社会生活に復帰し、ひと月目にはロードワークやウェイトトレーニングを開始していた。
日常生活には支障がないと、もぐりの医者の上田は口惜しそうに言った。
日常生活がどういうものかは、私が決定することだった。
長坂ジムでのスパーリングは、間違いなく私の日常生活なのだ。
しかし、練習生は私とのスパーリングを禁じられていたし、無理にリングに引っ張りあげた秋月は、決してボディを打とうとはしない。
秋月がかわいそうだという長坂の言葉は、確かに当たっているのかもしれない。
腰の後ろの手術痕は、トランクスからはみ出しているのだ。
ボクシングでは、秋月にさえまともに相手をして貰えなくなったが、私の日常生活でそれ以外に変ったことはなかった。
私は相変らず八木法律事務所の調査員であり、マセラーティ・スパイダーを転がし、レストラン『ミサ』の二階をねぐらにしている。
両膝から下がない八木の、脚代りであることも変りなかった。
シャワーを使っていると、秋月が入ってきた。
殴り倒されて失禁しているような坊やだったが、いまそんな真似ができるやつはあまりいないだろう。
痩せているが、筋肉だけでなく、躰の内側までしっかり鍛えていることが、見ただけでわかる。
躰の内側というのはボクシングでよく言うことで、つまりは打たれてもある程度はもちこたえられる内臓を持っているということだ。
そして私は、その内臓のひとつを失った。
これまでに失ってきたものと較べれば、取るに足りないものだ。
それでも、躰の外側から、その傷は見えてしまう。
「例の事件、きのう判決が出たんですよ。ボスに聞きました?」
秋月は、ボクシングと関係ないことを言った。
黙って、私は首を振った。
「また、無罪ですよ。黒いところに、主観のあやふやさと感情というミルクを流しこんで、灰色にしちまったんです。
検察は、控訴するかどうか、検討をはじめるようですが、半分は諦め顔でしたね」
私が調査した、些細な傷害事件だった。
検察は過剰防衛を主張し、私が調査したかぎりでもそんな感じだったが、八木は正当防衛を認めさせたのだろう。
八木法律事務所の仕事の半分は、海外との商取引のトラブルの対処だった。
成功報酬も、相当なものだという。
残りの半分は刑事事件で、殺人から強姦まで、ほとんど趣味としか思えないような仕事の受け方を、八木はしている。
それにおける事務所の収入はわずかなもので、全体の五パーセントにも満たないようだ。
八木がなぜ刑事事件をやるか、私にはわかるような気がした。
契約がどうのなどと言うより、人の姿がよく見えるからだ。
弱さも醜さも含めて、人が剥き出しになる。
そして八木は、自分の舌先だけで、犯罪者を自由にすることに、暗い情熱を燃やしているようにも見えた。
...続きは本書でどうぞ
