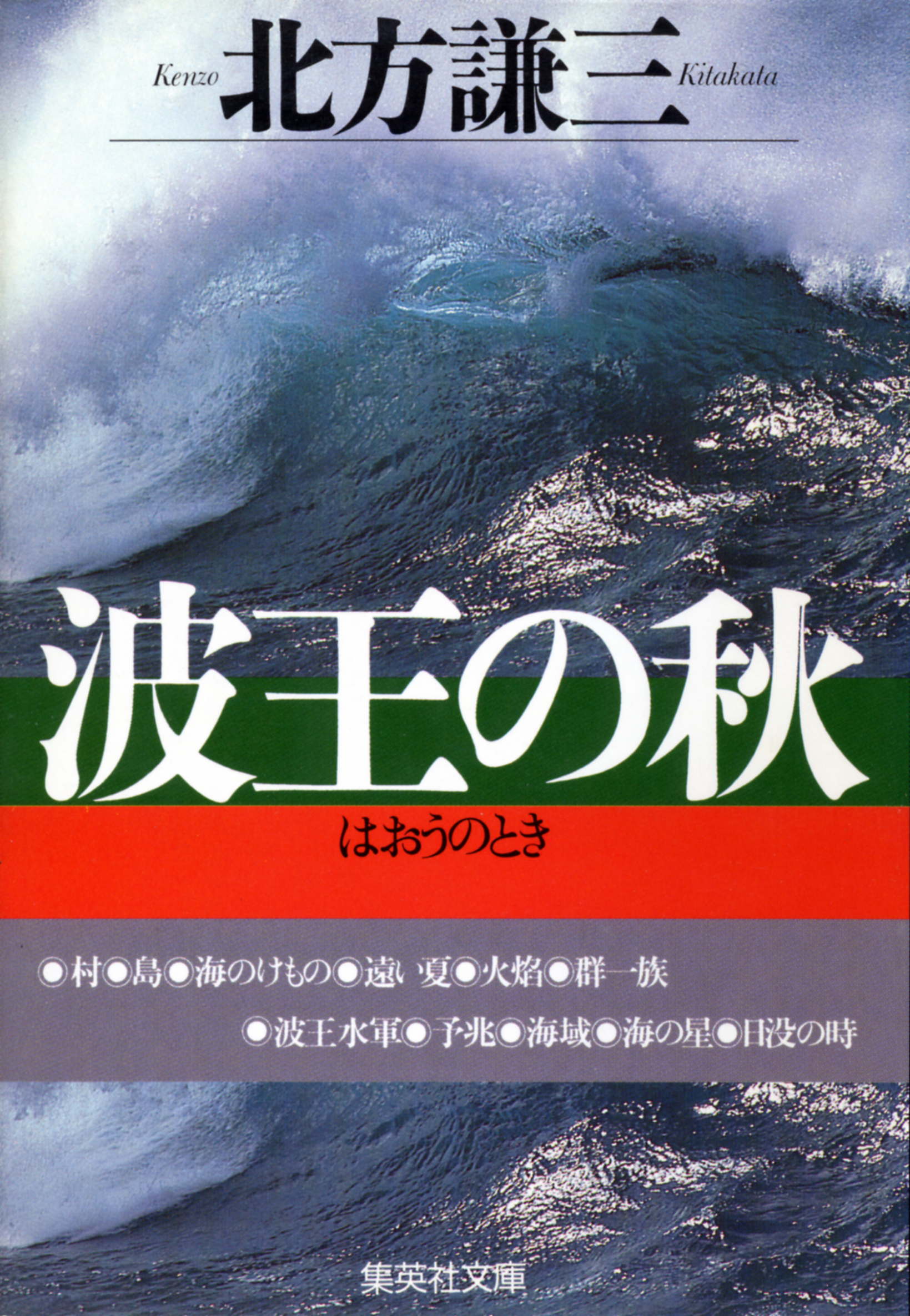
波王の秋
はおうのとき
時代は南北朝。
肥前のとある浜辺に一人の男が泳ぎついた。
密使だった。
済州島のナミノオオは、上松浦党水軍に手を結ぼうと持ちかける。
やがて両軍の後押しで、波王水軍が旗揚げされた。
若き上松浦党の跡継・小四郎を大将として。
海を祖国を護らねばならない。
熱き思いを胸に秘め、小四郎が立ちあがる。
敵は、強大な元朝。
そして決戦の時は、今。
大海原を舞台に描かれる北方歴史ハードボイルドの会心作。
時代は南北朝。
肥前のとある浜辺に一人の男が泳ぎついた。
密使だった。
済州島のナミノオオは、上松浦党水軍に手を結ぼうと持ちかける。
やがて両軍の後押しで、波王水軍が旗揚げされた。
若き上松浦党の跡継・小四郎を大将として。
海を祖国を護らねばならない。
熱き思いを胸に秘め、小四郎が立ちあがる。
敵は、強大な元朝。
そして決戦の時は、今。
大海原を舞台に描かれる北方歴史ハードボイルドの会心作。
<単行本>1996年 9月 刊行
<文庫本>1998年11月25日 初版発行
村
砂は、人の肌のような色をしていた。
海水からあがると、蹠からすぐに熱くなった。
強い陽射しである。
浜辺には風もなく、小波の音が静けさを逆に深めていた。
竜知勝は、頭に縛りつけてきた包みを解き、直垂を着こんだ。
侍烏帽子をつけると、もうどこから見ても武士である。
草鞋も履いた。
海鳥が頭上を過ぎていく。
鳥の姿が少ないのは、磯がないせいなのか。
浜をしばらく歩き続け、松林の中にようやく小径をひとつ見つけた。
どこにでも、人が通る道はあるものなのだ。
十数歩松林の中を進んだところで、竜知勝は足を止めた。
不意に、湧き立つように、林のそこここから気配が感じられるのである。
いきなり襲ってくるという感じではないが、威圧してくるものる。
「名乗れ」
声が、さきに聞えた。
下生えの、丈高い草の中から姿を現したのは、細身の童だった。
ただ、腰にはしっかりと太刀を佩いている。
「大友家の者で、竜村知安という。自ら名乗るのが先だ、と儂は思うがな」
この国の言葉と高麗の言葉を、竜知勝は完全に操れた。
父がこの国の男で、母は高麗の女だというが、知勝は二人とも顔すら知らなかった。
竜知勝という名も、両親から貰ったものではない。
「俺は波多家の者で、夏丸という。これでいいか?」
「よかろう」
「なにゆえ、大友家の家臣がここにいる?」
「高麗の船に拾われた。
儂の乗っていた船は、嵐で海に呑まれた。
漂っていたところを、助けてくれたのだ。
ただ、この国のどこの泊にも、船は入れたくないと言われた。
それで艀で岸近くまで来て、あとは泳いだのよ。
九州ならば、豊後には繋がっているだろうと思って、歩きはじめたばかりだ」
泳いでいるところから、ずっと見ていたのだろうと知勝は思った。
沖から艀を出した船は高麗のもので、艀を漕いできた二人も高麗の水師だ。
見られることを覚悟して、知勝はかなり深いところから泳いできた。
「なぜ、艀で浜まで来なかった?」
...続きは本書でどうぞ
砂は、人の肌のような色をしていた。
海水からあがると、蹠からすぐに熱くなった。
強い陽射しである。
浜辺には風もなく、小波の音が静けさを逆に深めていた。
竜知勝は、頭に縛りつけてきた包みを解き、直垂を着こんだ。
侍烏帽子をつけると、もうどこから見ても武士である。
草鞋も履いた。
海鳥が頭上を過ぎていく。
鳥の姿が少ないのは、磯がないせいなのか。
浜をしばらく歩き続け、松林の中にようやく小径をひとつ見つけた。
どこにでも、人が通る道はあるものなのだ。
十数歩松林の中を進んだところで、竜知勝は足を止めた。
不意に、湧き立つように、林のそこここから気配が感じられるのである。
いきなり襲ってくるという感じではないが、威圧してくるものる。
「名乗れ」
声が、さきに聞えた。
下生えの、丈高い草の中から姿を現したのは、細身の童だった。
ただ、腰にはしっかりと太刀を佩いている。
「大友家の者で、竜村知安という。自ら名乗るのが先だ、と儂は思うがな」
この国の言葉と高麗の言葉を、竜知勝は完全に操れた。
父がこの国の男で、母は高麗の女だというが、知勝は二人とも顔すら知らなかった。
竜知勝という名も、両親から貰ったものではない。
「俺は波多家の者で、夏丸という。これでいいか?」
「よかろう」
「なにゆえ、大友家の家臣がここにいる?」
「高麗の船に拾われた。
儂の乗っていた船は、嵐で海に呑まれた。
漂っていたところを、助けてくれたのだ。
ただ、この国のどこの泊にも、船は入れたくないと言われた。
それで艀で岸近くまで来て、あとは泳いだのよ。
九州ならば、豊後には繋がっているだろうと思って、歩きはじめたばかりだ」
泳いでいるところから、ずっと見ていたのだろうと知勝は思った。
沖から艀を出した船は高麗のもので、艀を漕いできた二人も高麗の水師だ。
見られることを覚悟して、知勝はかなり深いところから泳いできた。
「なぜ、艀で浜まで来なかった?」
...続きは本書でどうぞ
