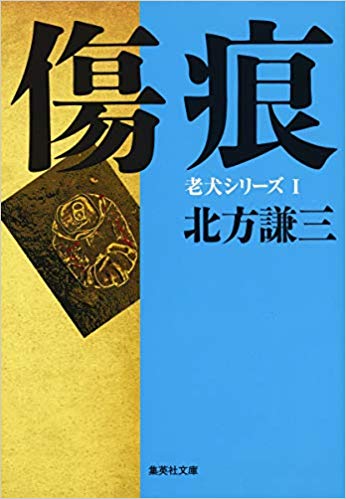
傷痕
しょうこん
老犬シリーズⅠ
孔雀城───無頼の少年たちは、自分たちの寝ぐらをそう呼んだ。
戦争直後の東京、焼けくずれた工場の跡地である。
隠匿物資を盗み出し、闇市で売りさばくことを覚えた良文とその仲間にとって、最大の敵は浮浪児狩りと暴力団だった。
幼い良文は野獣のように生き抜いてゆく。
「老いぼれ犬」高樹刑事の壮絶な少年時代。
老犬シリーズⅠ
孔雀城───無頼の少年たちは、自分たちの寝ぐらをそう呼んだ。
戦争直後の東京、焼けくずれた工場の跡地である。
隠匿物資を盗み出し、闇市で売りさばくことを覚えた良文とその仲間にとって、最大の敵は浮浪児狩りと暴力団だった。
幼い良文は野獣のように生き抜いてゆく。
「老いぼれ犬」高樹刑事の壮絶な少年時代。
<単行本>1989年 7月 刊行
<文庫本>1992年 9月25日 初版発行
第一章
息。
闇の中で聞こえるのは、それだけだった。
自分の息なのか幸太のものなのかも定かではない息に、じっと耳を傾けることで、良文は押し潰されそうになる気持をなんとか支え続けていた。
遠くで、男の声がした。カストリでも飲んで酔っているような声だ。
太いその声が、闇の底に響き、良文の胸にも躰にも響いた。
かすかな幸太の身動きの気配が伝わってくる。
自分を抑えるように、良文は幸太の肩に手をのばした。
男の声は、遠ざかっていった。
「酔っ払いなんかに、びくつくんじゃねえぞ、良」
びくついてはいなかった。
いるはずがない。
幸太の無神経さで、すべてを失敗に終わらせたくないだけだ。
良文は頭を掻きむしった。
シラミが髪の間で暴れ回っている。
「こんなのは、度胸だよ。それさえ決めてりゃ、大人だろうが子供だろうが、案山子みてえなもんじぇあねえか」
「喋るな、幸太」
「わかってる。だけどな、度胸を決めりゃ、突っ走るだけしかねえぞ」
なにがどこにあるのか、頭に入れたいた。
それを確かめるためだけに、四日も外食券一枚で働いたのだ。
それでも、防空壕には近づけなかった。
焼けた家の始末をし、針金を張った柵をこしらえただけだ。
そうやって働いている少年たちは、ほかに五人いた。
そのうちの三人は、外食券ではなく、ようやく一日分の腹を満たす芋を貰う方を選んだ。
子供を使うのは、大人の半分以下の金で済むためと、子供でもできないことはない、簡単な仕事だったからだろう。
おかしな気を起こすのも、大抵は大人だ。
良文は、闇の中をしばらく這った。
十メートルは進んだ、と思った。
幸太も、並んで進んできている。
防空壕まで、あと三十メートルというところだ。
そこまで行くためには、良文や幸太が、一日水団一杯分の金で造った、針金の柵がある。
「もうすぐ、柵じゃねんか、良」
幸太が耳元で囁いた。
闇の中では、距離はひどく測りにくく、昼間目印だと思ったものもほとんど見えはしなかった。
頭が痒い。
いまいましいほどだ。
このあたりはまだ、ほとんど掘立小屋も建っていなくて、焼けた時のままだった。
それが闇に溶け込んでしまっている。
月も星もないから、なおさらだった。
...続きは本書でどうぞ
息。
闇の中で聞こえるのは、それだけだった。
自分の息なのか幸太のものなのかも定かではない息に、じっと耳を傾けることで、良文は押し潰されそうになる気持をなんとか支え続けていた。
遠くで、男の声がした。カストリでも飲んで酔っているような声だ。
太いその声が、闇の底に響き、良文の胸にも躰にも響いた。
かすかな幸太の身動きの気配が伝わってくる。
自分を抑えるように、良文は幸太の肩に手をのばした。
男の声は、遠ざかっていった。
「酔っ払いなんかに、びくつくんじゃねえぞ、良」
びくついてはいなかった。
いるはずがない。
幸太の無神経さで、すべてを失敗に終わらせたくないだけだ。
良文は頭を掻きむしった。
シラミが髪の間で暴れ回っている。
「こんなのは、度胸だよ。それさえ決めてりゃ、大人だろうが子供だろうが、案山子みてえなもんじぇあねえか」
「喋るな、幸太」
「わかってる。だけどな、度胸を決めりゃ、突っ走るだけしかねえぞ」
なにがどこにあるのか、頭に入れたいた。
それを確かめるためだけに、四日も外食券一枚で働いたのだ。
それでも、防空壕には近づけなかった。
焼けた家の始末をし、針金を張った柵をこしらえただけだ。
そうやって働いている少年たちは、ほかに五人いた。
そのうちの三人は、外食券ではなく、ようやく一日分の腹を満たす芋を貰う方を選んだ。
子供を使うのは、大人の半分以下の金で済むためと、子供でもできないことはない、簡単な仕事だったからだろう。
おかしな気を起こすのも、大抵は大人だ。
良文は、闇の中をしばらく這った。
十メートルは進んだ、と思った。
幸太も、並んで進んできている。
防空壕まで、あと三十メートルというところだ。
そこまで行くためには、良文や幸太が、一日水団一杯分の金で造った、針金の柵がある。
「もうすぐ、柵じゃねんか、良」
幸太が耳元で囁いた。
闇の中では、距離はひどく測りにくく、昼間目印だと思ったものもほとんど見えはしなかった。
頭が痒い。
いまいましいほどだ。
このあたりはまだ、ほとんど掘立小屋も建っていなくて、焼けた時のままだった。
それが闇に溶け込んでしまっている。
月も星もないから、なおさらだった。
...続きは本書でどうぞ
