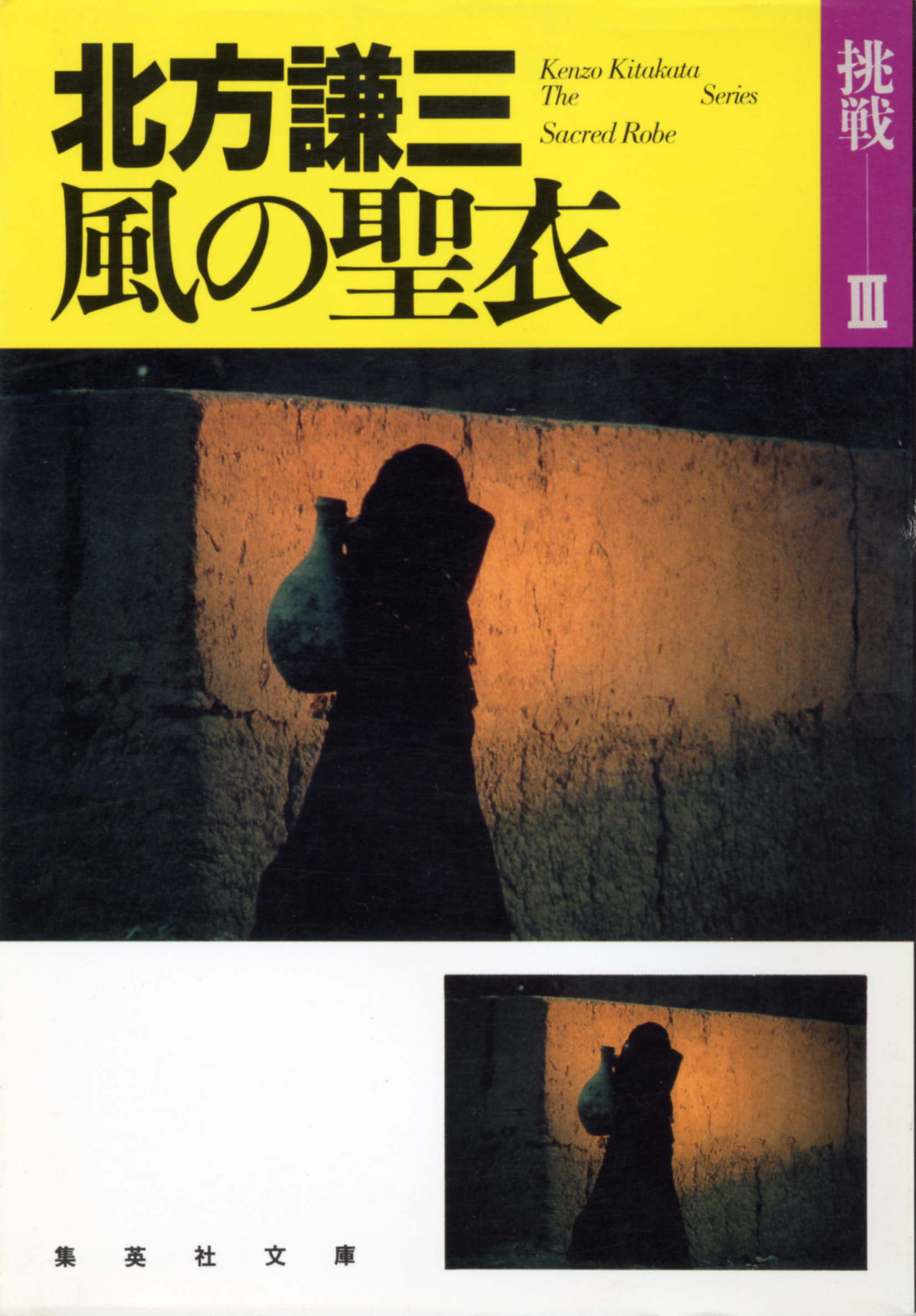
風の聖衣
かぜのせいい
挑戦シリーズⅢ
風吹きすさぶペルーの高山地帯。 「狼」と呼ばれ、ゲリラの指導者となり、村の守護神として尊敬を集めている水野竜一を村沢がつけ狙う。
彼は殺すべきではなかった男を射殺し、その心の傷をいやすべく傭兵となり、ペルーをさまよう元刑事だった。
村沢は「狼」の村の攻撃を計画、あらゆる手段をつかって「狼」をおびき寄せようとするが・・・。
挑戦シリーズⅢ
風吹きすさぶペルーの高山地帯。 「狼」と呼ばれ、ゲリラの指導者となり、村の守護神として尊敬を集めている水野竜一を村沢がつけ狙う。
彼は殺すべきではなかった男を射殺し、その心の傷をいやすべく傭兵となり、ペルーをさまよう元刑事だった。
村沢は「狼」の村の攻撃を計画、あらゆる手段をつかって「狼」をおびき寄せようとするが・・・。
<単行本>1987年10月 刊行
<文庫本>1990年 8月25日 初版発行
サンチャゴ・デ・クーパ
積荷を動かしている気配はなかった。
接岸して二時間以上経つが、ドアは開かなかった。
ダイナモのかすかな唸りが、ベッドに横たわったままの村沢の躰に伝わってくるだけだ。
煙草を一本喫った。
煙は、部屋からなかなか抜けていかない。
古い船で、航行中でなければ、換気装置はうまく働かないようだ。
室温もあがっていた。
首筋をつっと汗が流れ落ちていったが、村沢は大して気にもとめなかった。
ベラクルスを出航して、すでに三カ所ほど停泊してきた。
ここで降ろされるとは限らなかった。
五百トンほどの小さな貨物船。
船籍がパナマになっているのを乗船するときに見ただけで、あとは丸二日と半日、立てば頭が天井につかえてしまう狭い船室から、一歩も出ることを許されなかった。
いつの間にか、眠りに落ちかかっていた。
夢は見ない。
夢を押し殺すために浴びるように飲んだアルコールは、躰からは抜けきっているが、心からは抜けていなかった。
眠りは、ただ混濁だった。
ノック。
遠い。
それが近くなった。
鍵を回す音。
「下船だ」
髭面の白人が、ドアの隙間から冷たい視線を走らせて、短く言った。
村沢はのろのろとベッドから躰を起こし、靴を履いた。
荷物といえば、肩からかける小さなサックがひとつきりだ。
夕方。
甲板は、まだ陽射しの名残りで焼けていた。
吹き付けてくる風も、生温かい。
村沢は無精髭を指先でつまみながら、眩しそうな視線を岸壁にむけた。
眼差しは、癖だった。
熱帯の陽光から眼を守ろうとして、そうなってしまったのだ。
闇の中でも、そういう眼ざしをする。
岸壁で、男がひとり片手をあげているのに、村沢は眼をとめた。
自分が呼ばれているとしか思えなかった。
タラップとも言えないような木の板が、岸壁との間に渡してある。
乗ると、かなり揺れた。
岸壁に降り立つ。
倉庫などはあまり見当たらなくて、トラックが何台か並んでいるだけだ。
ほかに接岸している二隻の船も、数百トンの小さなものだった。
「待ってたよ」
スペイン語で言って、男は右手を差し出してきた。
軽く握り返す。
...続きは本書でどうぞ
積荷を動かしている気配はなかった。
接岸して二時間以上経つが、ドアは開かなかった。
ダイナモのかすかな唸りが、ベッドに横たわったままの村沢の躰に伝わってくるだけだ。
煙草を一本喫った。
煙は、部屋からなかなか抜けていかない。
古い船で、航行中でなければ、換気装置はうまく働かないようだ。
室温もあがっていた。
首筋をつっと汗が流れ落ちていったが、村沢は大して気にもとめなかった。
ベラクルスを出航して、すでに三カ所ほど停泊してきた。
ここで降ろされるとは限らなかった。
五百トンほどの小さな貨物船。
船籍がパナマになっているのを乗船するときに見ただけで、あとは丸二日と半日、立てば頭が天井につかえてしまう狭い船室から、一歩も出ることを許されなかった。
いつの間にか、眠りに落ちかかっていた。
夢は見ない。
夢を押し殺すために浴びるように飲んだアルコールは、躰からは抜けきっているが、心からは抜けていなかった。
眠りは、ただ混濁だった。
ノック。
遠い。
それが近くなった。
鍵を回す音。
「下船だ」
髭面の白人が、ドアの隙間から冷たい視線を走らせて、短く言った。
村沢はのろのろとベッドから躰を起こし、靴を履いた。
荷物といえば、肩からかける小さなサックがひとつきりだ。
夕方。
甲板は、まだ陽射しの名残りで焼けていた。
吹き付けてくる風も、生温かい。
村沢は無精髭を指先でつまみながら、眩しそうな視線を岸壁にむけた。
眼差しは、癖だった。
熱帯の陽光から眼を守ろうとして、そうなってしまったのだ。
闇の中でも、そういう眼ざしをする。
岸壁で、男がひとり片手をあげているのに、村沢は眼をとめた。
自分が呼ばれているとしか思えなかった。
タラップとも言えないような木の板が、岸壁との間に渡してある。
乗ると、かなり揺れた。
岸壁に降り立つ。
倉庫などはあまり見当たらなくて、トラックが何台か並んでいるだけだ。
ほかに接岸している二隻の船も、数百トンの小さなものだった。
「待ってたよ」
スペイン語で言って、男は右手を差し出してきた。
軽く握り返す。
...続きは本書でどうぞ
