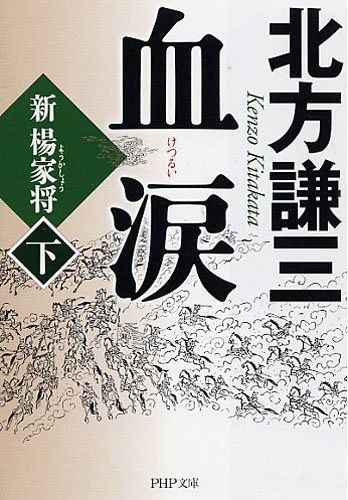
血涙 下
<文庫本>2009年 4月17日 初版発行
死生ともにありて
延光に言った。
旗は、六郎と話し合って決めたものだ。
それが、最もふさわしいものだろう、ということになった。
延平の嫡男で、最も年長である楊業の孫なのだ。
「叔父上の旗は?」
「俺は、闘うわけではない。おまえの戦を見物するだけだ。初陣にしては冴えない戦だが、とにかくここで勝て。それも、犠牲をできるだけ少なくしてだ。」
「はい」
「いずれ、耶律休哥とぶつかることもあるだろう。二千ぐらいの遼軍を追い散らせないようなら、手もなく負けるぞ」
「一兵も、失いません」
「そう堅苦しくなるな。戦に犠牲はつきものだ。ただ、頭に犠牲を少なくということがあるだけでいい。一兵も失うまいとすると、逆に動きが制限される」
「はい。気持としてそうだというだけで」
「もういい。すべては、実戦で見せてみろ」
延光が『延』の旗を揚げた。
代州軍は、打ち合わせた通り、川縁りにむかって進んできている。
川縁りの六千の代州軍は、いるだけで遼軍に対して大きな脅威になる。
それをうまく利用すれば、たとえ二、三百でも思うさまに掻きき回せる。
それぐらいは、延光には当然のこととしてわかっているはずだ。
不意に、はじめての実践の場に立たされた戸惑いも、見せていない。
「叔父上、俺が、俺の戦をやってもいい、ということですか?」
「俺の二百は、いないと思え」
「はい」
「では、渡渉から見物させて貰うぞ」
大きく頷き、延光は馬首を回した。
延光の渡渉は、大胆だった。
五隊を横列にし、駈けるでもなく堂々と渉っていく。
川縁りの遼軍の守備兵は、気圧されて退がりはじめていた。
五百騎のあとから、七郎は二百騎を率いて渡渉した。
延光の隊は、すでに二隊に別れて駈けていた。
正面突破したのちの反転。
川縁りにまで進んできている。
六千の代州軍を充分に生かしたやり方だった。
思った通り、延光の隊は変幻に五隊に分かれ、ひとつになり、ぶつかる瞬間は楔の隊形をとり、あっという間に二千の遼軍の中央を突破した。
反転は、速かった。
しかも横列である。
二千の全部に、圧力をかけている。
そういう時は、どこかが崩れる。
思った通り、左翼が浮足立っていた。
延光の軍は、ぶつかる寸前に小さくかたまり、左翼に攻撃を集中した。
延光は、戦況を正確に見きわめられる眼を持っている。
そして、判断が早い。
兵の調練も、充分にできていた。
「まずまずか」
七郎は呟いた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
延光に言った。
旗は、六郎と話し合って決めたものだ。
それが、最もふさわしいものだろう、ということになった。
延平の嫡男で、最も年長である楊業の孫なのだ。
「叔父上の旗は?」
「俺は、闘うわけではない。おまえの戦を見物するだけだ。初陣にしては冴えない戦だが、とにかくここで勝て。それも、犠牲をできるだけ少なくしてだ。」
「はい」
「いずれ、耶律休哥とぶつかることもあるだろう。二千ぐらいの遼軍を追い散らせないようなら、手もなく負けるぞ」
「一兵も、失いません」
「そう堅苦しくなるな。戦に犠牲はつきものだ。ただ、頭に犠牲を少なくということがあるだけでいい。一兵も失うまいとすると、逆に動きが制限される」
「はい。気持としてそうだというだけで」
「もういい。すべては、実戦で見せてみろ」
延光が『延』の旗を揚げた。
代州軍は、打ち合わせた通り、川縁りにむかって進んできている。
川縁りの六千の代州軍は、いるだけで遼軍に対して大きな脅威になる。
それをうまく利用すれば、たとえ二、三百でも思うさまに掻きき回せる。
それぐらいは、延光には当然のこととしてわかっているはずだ。
不意に、はじめての実践の場に立たされた戸惑いも、見せていない。
「叔父上、俺が、俺の戦をやってもいい、ということですか?」
「俺の二百は、いないと思え」
「はい」
「では、渡渉から見物させて貰うぞ」
大きく頷き、延光は馬首を回した。
延光の渡渉は、大胆だった。
五隊を横列にし、駈けるでもなく堂々と渉っていく。
川縁りの遼軍の守備兵は、気圧されて退がりはじめていた。
五百騎のあとから、七郎は二百騎を率いて渡渉した。
延光の隊は、すでに二隊に別れて駈けていた。
正面突破したのちの反転。
川縁りにまで進んできている。
六千の代州軍を充分に生かしたやり方だった。
思った通り、延光の隊は変幻に五隊に分かれ、ひとつになり、ぶつかる瞬間は楔の隊形をとり、あっという間に二千の遼軍の中央を突破した。
反転は、速かった。
しかも横列である。
二千の全部に、圧力をかけている。
そういう時は、どこかが崩れる。
思った通り、左翼が浮足立っていた。
延光の軍は、ぶつかる寸前に小さくかたまり、左翼に攻撃を集中した。
延光は、戦況を正確に見きわめられる眼を持っている。
そして、判断が早い。
兵の調練も、充分にできていた。
「まずまずか」
七郎は呟いた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
