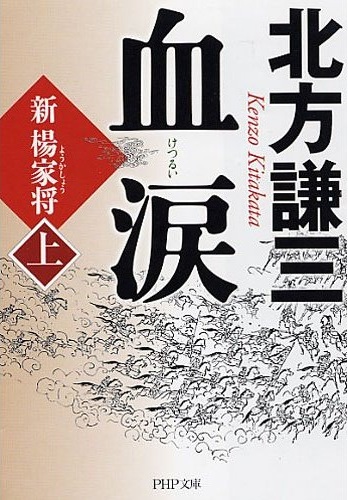
血涙 上
<文庫本>2009年 4月17日 初版発行
砂の声
風で砂が逆巻くと、兵たちは眼に板を当てる。
小さな穴が穿ってあり、わずかだが視界は確保できる。
枚とともに、いつも兵に身につけさせているものだ。
いまの遼軍に、砂を防ぐ板は必要なかった。
燕雲十六州を押さえ、さらに南下する勢いだから、草原での戦が多くなる。
たとえ砂漠での戦になっても、宋軍より遙かに砂の防ぎ方は知っているのだ。
それでも、耶律休哥は、砂との闘いを兵に叩き込んだ。
自分の軍は、砂の上で生まれ、強くなってきたのだと思う。
砂とともに生きた、と言ってもいいだろう。
水が極端に少ない北辺は、冬でも砂が舞う。
夏の砂と違って、空を曇らせたりはしないが、氷の粒のように兵たちを打つ。
夏の砂は、煙のような粉で、時に陽を隠してしまう。
この北辺の地が、耶律休哥は好きだった。
追いやられてここへ来たようなものだが、はじめからこの地が好きになった。
樹木や池や豊かな草など、人の心を緩ませるものがほとんどない。
営舎を建てることさえ許されず、幕舎で暮らした。
弱い兵は死に、強い兵だけが残った。
麾下はすべて、騎馬隊である。
宋との度重なる戦での軍功が認められ、いまは五千騎を擁していた。
これ以上の増強も認められるだろうが、耶律休哥にそのつもりはなかった。
自らの手足のように動かせる軍としては、この数が限界だろう。
宋とは、休戦状態だった。
一昨年の戦は、両軍をともに疲弊させた。
遼では、軍の頂点にいた耶律奚低が戦死し、軍の編成がようやく終わったところだった。
その中でも、耶律休哥の軍だけは手がつけられず、独立行動権も与えられたままだった。
北辺の地から動かず、ひらすらに兵を鍛え、馬を養った。
いまでは、軍営を作ることも許されたいるが、泉のそばに営舎を建てただけだった。
防塁も防壁もない。
半数の兵は、いつも幕舎による野営をさせていた。
宋との戦が、終わったわけではない。
一昨年の宗主による親征より、もっと大きな軍を出してくる可能性は、たえずあった。
その時は、最初に前線に出るのは自分だろう。
麻哩阿吉が、野営から帰還の報告に来た。
石幻果が一緒である。
麻哩阿吉は、副官として力をつけてきたが、それでも石幻果には及ばない。
耶律休哥がはっとするほどの天性を、石幻果はしばしば見せるのだ。
「軍の状態は、申し分ないと私は思います」
「空を翔べるのか?」
「はっ?」
「兵たちが空を翔べたら、俺は申し分ないと言おう」
そばに立っていた石幻果が、低い笑い声をあげた。
耶律休哥はそれを無視し、細かい報告を受けた。
兵ひとりひとりの事まで、麻哩阿吉は把握しているようだ。
(…この続きは本書にてどうぞ)
風で砂が逆巻くと、兵たちは眼に板を当てる。
小さな穴が穿ってあり、わずかだが視界は確保できる。
枚とともに、いつも兵に身につけさせているものだ。
いまの遼軍に、砂を防ぐ板は必要なかった。
燕雲十六州を押さえ、さらに南下する勢いだから、草原での戦が多くなる。
たとえ砂漠での戦になっても、宋軍より遙かに砂の防ぎ方は知っているのだ。
それでも、耶律休哥は、砂との闘いを兵に叩き込んだ。
自分の軍は、砂の上で生まれ、強くなってきたのだと思う。
砂とともに生きた、と言ってもいいだろう。
水が極端に少ない北辺は、冬でも砂が舞う。
夏の砂と違って、空を曇らせたりはしないが、氷の粒のように兵たちを打つ。
夏の砂は、煙のような粉で、時に陽を隠してしまう。
この北辺の地が、耶律休哥は好きだった。
追いやられてここへ来たようなものだが、はじめからこの地が好きになった。
樹木や池や豊かな草など、人の心を緩ませるものがほとんどない。
営舎を建てることさえ許されず、幕舎で暮らした。
弱い兵は死に、強い兵だけが残った。
麾下はすべて、騎馬隊である。
宋との度重なる戦での軍功が認められ、いまは五千騎を擁していた。
これ以上の増強も認められるだろうが、耶律休哥にそのつもりはなかった。
自らの手足のように動かせる軍としては、この数が限界だろう。
宋とは、休戦状態だった。
一昨年の戦は、両軍をともに疲弊させた。
遼では、軍の頂点にいた耶律奚低が戦死し、軍の編成がようやく終わったところだった。
その中でも、耶律休哥の軍だけは手がつけられず、独立行動権も与えられたままだった。
北辺の地から動かず、ひらすらに兵を鍛え、馬を養った。
いまでは、軍営を作ることも許されたいるが、泉のそばに営舎を建てただけだった。
防塁も防壁もない。
半数の兵は、いつも幕舎による野営をさせていた。
宋との戦が、終わったわけではない。
一昨年の宗主による親征より、もっと大きな軍を出してくる可能性は、たえずあった。
その時は、最初に前線に出るのは自分だろう。
麻哩阿吉が、野営から帰還の報告に来た。
石幻果が一緒である。
麻哩阿吉は、副官として力をつけてきたが、それでも石幻果には及ばない。
耶律休哥がはっとするほどの天性を、石幻果はしばしば見せるのだ。
「軍の状態は、申し分ないと私は思います」
「空を翔べるのか?」
「はっ?」
「兵たちが空を翔べたら、俺は申し分ないと言おう」
そばに立っていた石幻果が、低い笑い声をあげた。
耶律休哥はそれを無視し、細かい報告を受けた。
兵ひとりひとりの事まで、麻哩阿吉は把握しているようだ。
(…この続きは本書にてどうぞ)
