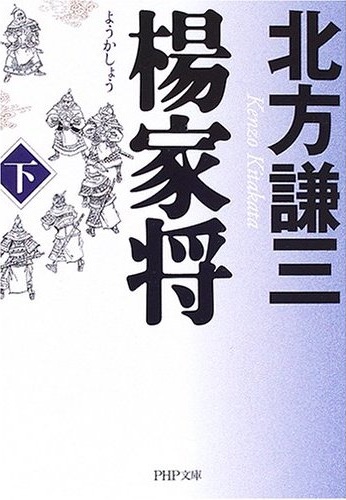
楊家将 下
国境を挟み、宋遼二国は一触即発の状態に。
伝説の英雄・楊業と息子たちの前に、遼の名将・耶律休哥が立ちはばかる。
白い毛をたなびかせて北の土漠を疾駆するこの男は、「白き狼」と恐れられていた。
宋軍生え抜きの将軍たちも、楊一族に次々と難問を突き付ける。
決戦の秋!
運命に導かれるようにして戦場に向かう男たち。
滅びゆく者たちの叫びが戦場に谺する。
北方『楊家将』、慟哭の終章。
国境を挟み、宋遼二国は一触即発の状態に。
伝説の英雄・楊業と息子たちの前に、遼の名将・耶律休哥が立ちはばかる。
白い毛をたなびかせて北の土漠を疾駆するこの男は、「白き狼」と恐れられていた。
宋軍生え抜きの将軍たちも、楊一族に次々と難問を突き付ける。
決戦の秋!
運命に導かれるようにして戦場に向かう男たち。
滅びゆく者たちの叫びが戦場に谺する。
北方『楊家将』、慟哭の終章。
<単行本>2003年12月 刊行
<文庫本>2006年 7月19日 初版発行
前夜
開封の楊家の館が、七郎にはあまり居心地のよいものではなかった。
というより、都そのものが、七郎は好きになれないのかもしれなかった。
ともに都に上った五郎は、しばしば内城の歓楽の巷に出かけているようだが、七郎が館を出るのは、遠乗りか、八王に召し出された時だけである。
八王からの使者は、三日に一度は来た。
長兄の延平と二郎は、妻帯していた。
三郎と五郎は、妻帯という気持はまるでないらしく、四郎は北平塞に行かされたままである。
六郎に妻帯の話が出ていて、本人も悪い気がしていないようだった。
いずれにせよ、妻帯など、七郎にはまだ遠い話だった。
開封府に、戦の雰囲気はまるでなかった。
遂城攻撃軍として編成された敵に、痛撃を与えた。
それによって遼は守勢に回り、数年は戦がないだろうというのが、文官のみならず、開封府の将軍たちの考えであるらしい。
三千の部下のうちの一千を失った、四郎の敗北など、開封では知っているものさえいなかった。
「北辺では、戦なのだぞ、王貴殿。耶律休哥が、応州に配置されるという噂もある。俺は、都で浮かれていたくない」
七郎が、夜の酒をともに飲むのは、王貴だけだった。
もの心ついた時から、王貴はいつも父のそばにいて、どこか叔父に対するような感情もある。
養母の佘賽花については、そういうわけにはいかなかった。
七郎の母は延平と三郎の母の呂氏の使用人で、呂氏の死後に父が手をつけ、自分が生まれたのだという。
佘賽花は、六郎や八郎、九妹の実母である。
「七郎殿の気持はよくわかるが、よくも悪くもこれが宋という国の都だ、というのも見ておいた方がいい。それから、宮中というのがどういうものかも」
「八王様に、しばしば呼ばれるのだが、どうしてもあの空気には馴染めない。王貴殿は、馴染めるのか?」
「馴染んでいる。そういうふりをするだけでいいのだ。私など、はじめからそうだった。軍の中には、楊家を快く思わない者もいる。それがどんな人間かも、七郎殿の眼で見定めておくことだ」
代州にも春が来ていたが、開封には初夏の光さえ射しているように、七郎には思えた。
こういう陽の光の中では、思うさま原野を駆け回りたい。
(…この続きは本書にてどうぞ)
開封の楊家の館が、七郎にはあまり居心地のよいものではなかった。
というより、都そのものが、七郎は好きになれないのかもしれなかった。
ともに都に上った五郎は、しばしば内城の歓楽の巷に出かけているようだが、七郎が館を出るのは、遠乗りか、八王に召し出された時だけである。
八王からの使者は、三日に一度は来た。
長兄の延平と二郎は、妻帯していた。
三郎と五郎は、妻帯という気持はまるでないらしく、四郎は北平塞に行かされたままである。
六郎に妻帯の話が出ていて、本人も悪い気がしていないようだった。
いずれにせよ、妻帯など、七郎にはまだ遠い話だった。
開封府に、戦の雰囲気はまるでなかった。
遂城攻撃軍として編成された敵に、痛撃を与えた。
それによって遼は守勢に回り、数年は戦がないだろうというのが、文官のみならず、開封府の将軍たちの考えであるらしい。
三千の部下のうちの一千を失った、四郎の敗北など、開封では知っているものさえいなかった。
「北辺では、戦なのだぞ、王貴殿。耶律休哥が、応州に配置されるという噂もある。俺は、都で浮かれていたくない」
七郎が、夜の酒をともに飲むのは、王貴だけだった。
もの心ついた時から、王貴はいつも父のそばにいて、どこか叔父に対するような感情もある。
養母の佘賽花については、そういうわけにはいかなかった。
七郎の母は延平と三郎の母の呂氏の使用人で、呂氏の死後に父が手をつけ、自分が生まれたのだという。
佘賽花は、六郎や八郎、九妹の実母である。
「七郎殿の気持はよくわかるが、よくも悪くもこれが宋という国の都だ、というのも見ておいた方がいい。それから、宮中というのがどういうものかも」
「八王様に、しばしば呼ばれるのだが、どうしてもあの空気には馴染めない。王貴殿は、馴染めるのか?」
「馴染んでいる。そういうふりをするだけでいいのだ。私など、はじめからそうだった。軍の中には、楊家を快く思わない者もいる。それがどんな人間かも、七郎殿の眼で見定めておくことだ」
代州にも春が来ていたが、開封には初夏の光さえ射しているように、七郎には思えた。
こういう陽の光の中では、思うさま原野を駆け回りたい。
(…この続きは本書にてどうぞ)
