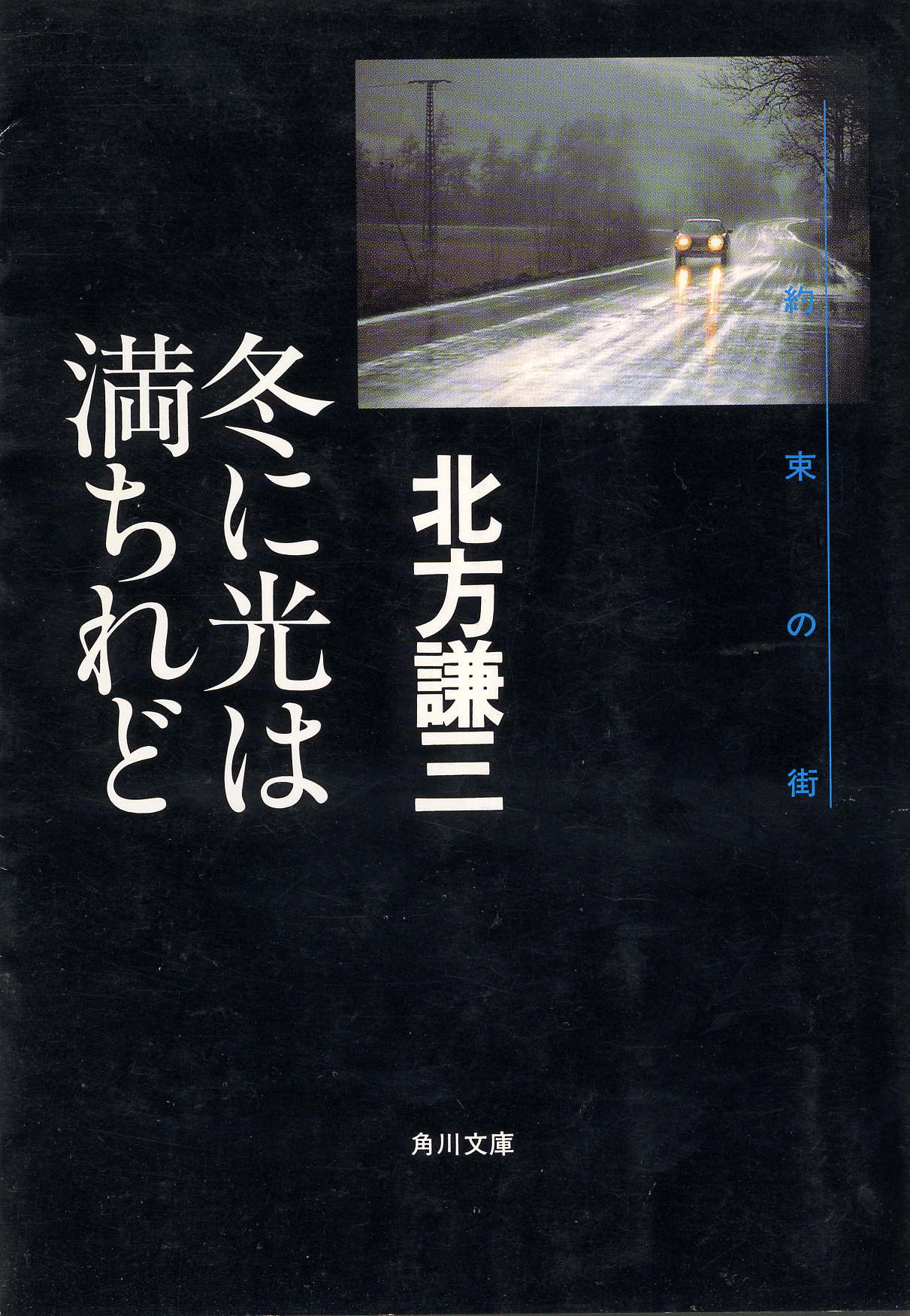
冬に光は満ちれど
約束の街③ (ブラディ・ドール13)
郊外のトンネルを抜けると蜃気楼のような街が目の前に広がる。
私はかつての師・市来を捜すためにこの街にやってきた。
三千万円の報酬で人ひとりの命を葬る。それが、彼に叩きこまれた私の仕事だった。
五年前、この稼業から互いに身を退いた。
なのに何故、市来は今、ひとりで仕事を踏もうとしているのか。
老いぼれた躯で何ができるというのか。
私が代わりに、標的を殺るしか、もはや止める術はなかった・・・・。
凪いだ歳月を辿る人生とは無縁な男たちの哀しみを謳う孤高の長編ハードボイルド。
約束の街③ (ブラディ・ドール13)
郊外のトンネルを抜けると蜃気楼のような街が目の前に広がる。
私はかつての師・市来を捜すためにこの街にやってきた。
三千万円の報酬で人ひとりの命を葬る。それが、彼に叩きこまれた私の仕事だった。
五年前、この稼業から互いに身を退いた。
なのに何故、市来は今、ひとりで仕事を踏もうとしているのか。
老いぼれた躯で何ができるというのか。
私が代わりに、標的を殺るしか、もはや止める術はなかった・・・・。
凪いだ歳月を辿る人生とは無縁な男たちの哀しみを謳う孤高の長編ハードボイルド。
<単行本>平成7年 2月 刊行
<文庫本>平成9年11月25日 初版発行
クラブ
目立つ男ではなかった。
百人の人間の中にいると、紛れてします。
名前を呼ばれるとしても最後で、誰もが聞き逃し、本人が手を挙げたとしても無視されてしまう。
そういう男だ。
ほとんど手掛かりもなく捜すのは、やはり難しそうだった。
この街の人口は一万八千ほどで、昼間はその二倍にはなるらしい。
そして何千人か何万人か知らないが、観光客もいる。
いや、観光客とは言えないかもしれない。
一番安いホテルでも、かなりの値段を取る。
金持ばかりが集まる、リゾートというやつだ。
私は、マスタングを路肩に寄せた。
ありふれた車だ。
この街を二時間ほど走り回っても、一台も出会いはしなかったが、それでもありふれている。
スタイルも、色も、転がしている人間もだ。
幼いころ、私はマスタングという車に憧れていた。
それだけの理由で、私はマスタングを買った。
望みというやつ。
満たされたことは、一度もない。
名前だけ同じ、別の車で満足するしかなかった。
助手席のコートを摑んで、、車を降りた。
着るまでのことは、なさそうだった。
舗道をちょっと歩いたところに、『スコーピオン』という喫茶店の看板が見える。
扉を押すと、女の声が迎えた。
私は、窓際の席に腰を降ろした。
コーヒーを頼む。
夜は酒も飲ませるのか、カウンターの棚にはウイスキーが並んでいた。
「キリマンジャロか」
運ばれてきたコーヒーの香りだけで、私はそう呟いた。
ええ、という女の子の返事が返ってくる。
話しかけたわけではなかった。
しかし幸先はいい。
くわえていた煙草を消した。
キャメル・フィルター。
それ以外は喫わない。
受け皿ごと、コーヒーに手をのばした。
そうやって飲むのも、私のやり方だった。
私のやり方が、そう沢山あるわけではなかった。
両手の指で数えられるほどのやり方があり、それが私を縛りあげている。
それだけのことだ。
味は悪くないコーヒーだった。
ネルで漉しているようだ。
受け皿を持ったまま、冷める前に私はコーヒーを飲み干した。
どうやって、探せばいいのか。
新しい煙草に火をつけて、私は考えはじめた。
どこかのホテルに泊まっているにしても、これでは探すのは大変だった。
警察手帳でもないかぎり、ホテルのフロントも宿泊客のことを喋りたがらないだろう。
金持相手ということは、そういうことだ。
...続きは本書でどうぞ
目立つ男ではなかった。
百人の人間の中にいると、紛れてします。
名前を呼ばれるとしても最後で、誰もが聞き逃し、本人が手を挙げたとしても無視されてしまう。
そういう男だ。
ほとんど手掛かりもなく捜すのは、やはり難しそうだった。
この街の人口は一万八千ほどで、昼間はその二倍にはなるらしい。
そして何千人か何万人か知らないが、観光客もいる。
いや、観光客とは言えないかもしれない。
一番安いホテルでも、かなりの値段を取る。
金持ばかりが集まる、リゾートというやつだ。
私は、マスタングを路肩に寄せた。
ありふれた車だ。
この街を二時間ほど走り回っても、一台も出会いはしなかったが、それでもありふれている。
スタイルも、色も、転がしている人間もだ。
幼いころ、私はマスタングという車に憧れていた。
それだけの理由で、私はマスタングを買った。
望みというやつ。
満たされたことは、一度もない。
名前だけ同じ、別の車で満足するしかなかった。
助手席のコートを摑んで、、車を降りた。
着るまでのことは、なさそうだった。
舗道をちょっと歩いたところに、『スコーピオン』という喫茶店の看板が見える。
扉を押すと、女の声が迎えた。
私は、窓際の席に腰を降ろした。
コーヒーを頼む。
夜は酒も飲ませるのか、カウンターの棚にはウイスキーが並んでいた。
「キリマンジャロか」
運ばれてきたコーヒーの香りだけで、私はそう呟いた。
ええ、という女の子の返事が返ってくる。
話しかけたわけではなかった。
しかし幸先はいい。
くわえていた煙草を消した。
キャメル・フィルター。
それ以外は喫わない。
受け皿ごと、コーヒーに手をのばした。
そうやって飲むのも、私のやり方だった。
私のやり方が、そう沢山あるわけではなかった。
両手の指で数えられるほどのやり方があり、それが私を縛りあげている。
それだけのことだ。
味は悪くないコーヒーだった。
ネルで漉しているようだ。
受け皿を持ったまま、冷める前に私はコーヒーを飲み干した。
どうやって、探せばいいのか。
新しい煙草に火をつけて、私は考えはじめた。
どこかのホテルに泊まっているにしても、これでは探すのは大変だった。
警察手帳でもないかぎり、ホテルのフロントも宿泊客のことを喋りたがらないだろう。
金持相手ということは、そういうことだ。
...続きは本書でどうぞ
