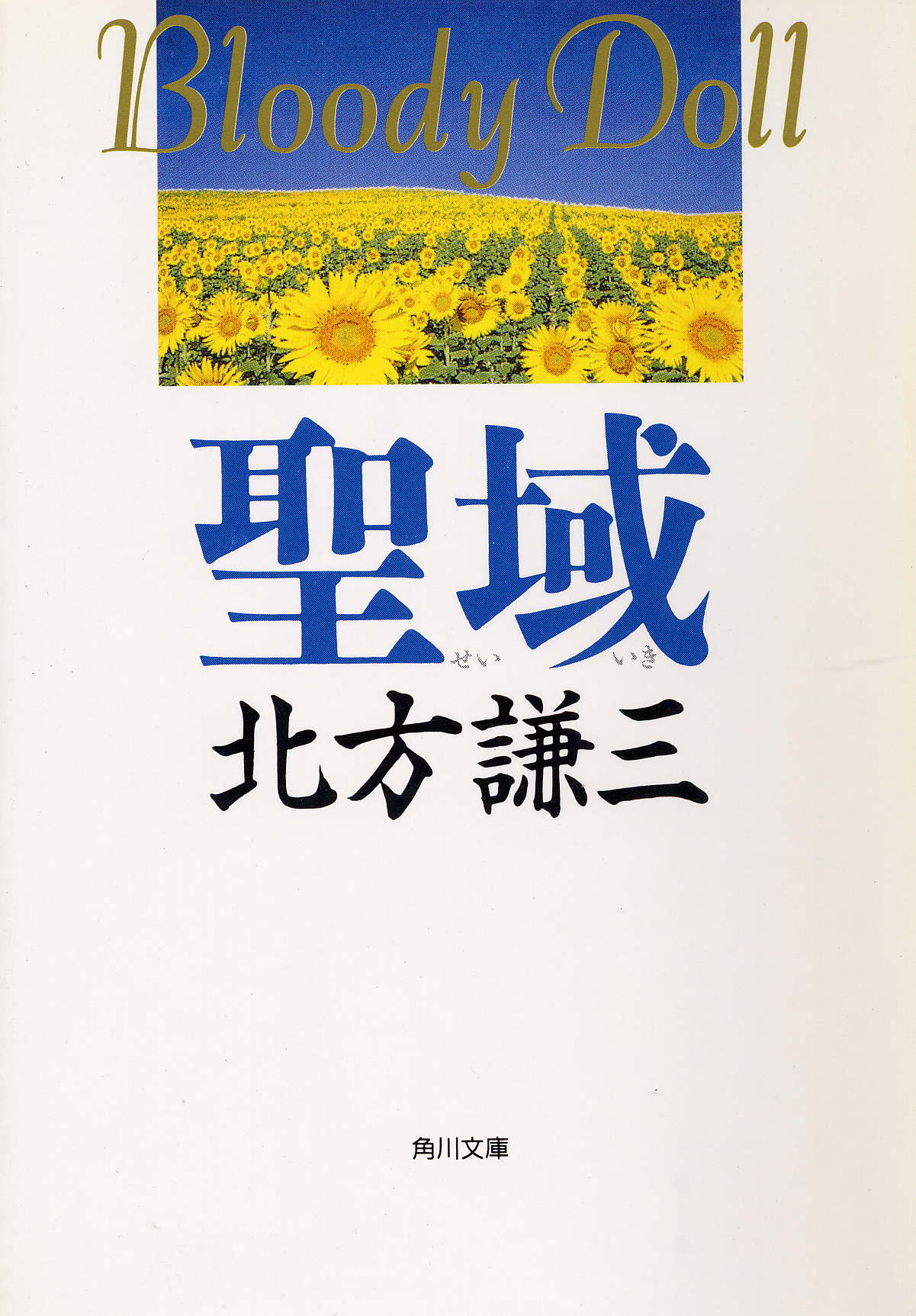
聖域 せいいき
“ブラディ・ドール”シリーズ 9
高校教師の西尾は、突然退学した生徒を探しにその街にやってきた。
「臆病なんですよ、俺は。自分でも情けなくなる・・・・」西尾はそう呟く。
だが、それでも自分を信じたいと思う。
沈黙しつづけるばかりの人生に幕を下ろしたいと、西尾は願った。
西尾は教え子が、暴力団に川中を殺るための鉄砲玉として雇われていることを知る。
一体なんのために・・・。
しかし、黙したまま墜ちていこうとした少年の決意を知ったとき、
西尾の魂の火がついた──。
己の魂の再生に賭けた男の姿を描くシリーズ第9弾!
“ブラディ・ドール”シリーズ 9
高校教師の西尾は、突然退学した生徒を探しにその街にやってきた。
「臆病なんですよ、俺は。自分でも情けなくなる・・・・」西尾はそう呟く。
だが、それでも自分を信じたいと思う。
沈黙しつづけるばかりの人生に幕を下ろしたいと、西尾は願った。
西尾は教え子が、暴力団に川中を殺るための鉄砲玉として雇われていることを知る。
一体なんのために・・・。
しかし、黙したまま墜ちていこうとした少年の決意を知ったとき、
西尾の魂の火がついた──。
己の魂の再生に賭けた男の姿を描くシリーズ第9弾!
<単行本>平成3年7月 刊行
<文庫本>平成5年3月25日 初版発行
ボーイ
店の中の空気を、天井からぶら下がった三枚羽根の扇風機がゆるやかにかき回し、煙草の煙やクーラーの冷気をほどよく拡散させ、私の前の置かれたコーヒーカップからたちのぼる香りだけが、夏の午後の光の中で際立っていた。
私は、開いていた歴史年表を閉じ、海の方へ眼をやった。
砂浜はあるが、海水浴は禁止されているらしく、歩いている人の姿が二つ三つ見えるだけだ。
泳ぐには、海流が強すぎる海岸なのかもしれない。
半島のむこう側には長い海岸線があり、そこには海の家が建ち並んで、砂浜も色とりどりのビーチパラソルで彩られていた。
店の中は静かで、低いジャズが流れているだけだ。
私以外に、客は四人いる。
四人とも、ただコーヒーを愉しんでいるように見えた。
アイスコーヒーなどは、誰も飲んでいない。
コーヒーを飲み干すと、私はサングラスをはずして、ハンカチで拭った。
度は入っている。
夜の運転のために、グローブボックスには普通の眼鏡も入っているが、私はサングラスをかけた自分の顔の方が好きだった。
外で、底力のあるエンジン音がした。
フェラーリのものだということは、音を聞いただけでわかったが、型まではわからなかった。
ドアが開く。
隙間からちょっと覗くと、ボディの一部が見えた。
赤いフェラーリ328。
最新型というわけではない。
東京から遊びに来た車だろうと思ったが、乗ってきたのは若い男で、カウンターのスツールに腰を降ろすと、アルバイトらしいウェイトレスの女の子と喋りはじめた。
この街にも、フェラーリを乗り回す若者がいるらしい。
私は腰をあげ、コーヒー代を払うと、ドアを押して強い陽射しの中に出た。
フェラーリ328は、私の白いカローラの隣にうずくまっていた。
やはり、地元の車だ。
私はそれを横目で見ながら、カローラに乗りこんでエンジンをかけた。
3万二千キロ走った、カローラ・レビン。
その気になれば、フェラーリと張り合う自信もあった。
サスペンションやブレーキのチューンはもとより、エンジンの圧縮比もあげている。
チューンの費用まで含めると、三百万を超える車だ。
駐車場から車を出し、私は海沿いの道を走って、街に入った。
最初に、ホテルを探した。
私がやろうとしていることが、東京から日帰りで済むような、簡単なことではないのはわかっている。
街の中心に向かう途中で、『シティホテル』というのが見つかった。
そこそこのホテルだ。
私はそこにチェック・インし、荷物だけ放り込むと、フロントで道を訊いて、日吉町にむかった。
田舎町だと思っていたが、意外に広い。
中心街から外れると、やがて古い街並みになり、さらに川を渡ると、新興住宅街が続いていた。
...続きは本書でどうぞ
店の中の空気を、天井からぶら下がった三枚羽根の扇風機がゆるやかにかき回し、煙草の煙やクーラーの冷気をほどよく拡散させ、私の前の置かれたコーヒーカップからたちのぼる香りだけが、夏の午後の光の中で際立っていた。
私は、開いていた歴史年表を閉じ、海の方へ眼をやった。
砂浜はあるが、海水浴は禁止されているらしく、歩いている人の姿が二つ三つ見えるだけだ。
泳ぐには、海流が強すぎる海岸なのかもしれない。
半島のむこう側には長い海岸線があり、そこには海の家が建ち並んで、砂浜も色とりどりのビーチパラソルで彩られていた。
店の中は静かで、低いジャズが流れているだけだ。
私以外に、客は四人いる。
四人とも、ただコーヒーを愉しんでいるように見えた。
アイスコーヒーなどは、誰も飲んでいない。
コーヒーを飲み干すと、私はサングラスをはずして、ハンカチで拭った。
度は入っている。
夜の運転のために、グローブボックスには普通の眼鏡も入っているが、私はサングラスをかけた自分の顔の方が好きだった。
外で、底力のあるエンジン音がした。
フェラーリのものだということは、音を聞いただけでわかったが、型まではわからなかった。
ドアが開く。
隙間からちょっと覗くと、ボディの一部が見えた。
赤いフェラーリ328。
最新型というわけではない。
東京から遊びに来た車だろうと思ったが、乗ってきたのは若い男で、カウンターのスツールに腰を降ろすと、アルバイトらしいウェイトレスの女の子と喋りはじめた。
この街にも、フェラーリを乗り回す若者がいるらしい。
私は腰をあげ、コーヒー代を払うと、ドアを押して強い陽射しの中に出た。
フェラーリ328は、私の白いカローラの隣にうずくまっていた。
やはり、地元の車だ。
私はそれを横目で見ながら、カローラに乗りこんでエンジンをかけた。
3万二千キロ走った、カローラ・レビン。
その気になれば、フェラーリと張り合う自信もあった。
サスペンションやブレーキのチューンはもとより、エンジンの圧縮比もあげている。
チューンの費用まで含めると、三百万を超える車だ。
駐車場から車を出し、私は海沿いの道を走って、街に入った。
最初に、ホテルを探した。
私がやろうとしていることが、東京から日帰りで済むような、簡単なことではないのはわかっている。
街の中心に向かう途中で、『シティホテル』というのが見つかった。
そこそこのホテルだ。
私はそこにチェック・インし、荷物だけ放り込むと、フロントで道を訊いて、日吉町にむかった。
田舎町だと思っていたが、意外に広い。
中心街から外れると、やがて古い街並みになり、さらに川を渡ると、新興住宅街が続いていた。
...続きは本書でどうぞ
