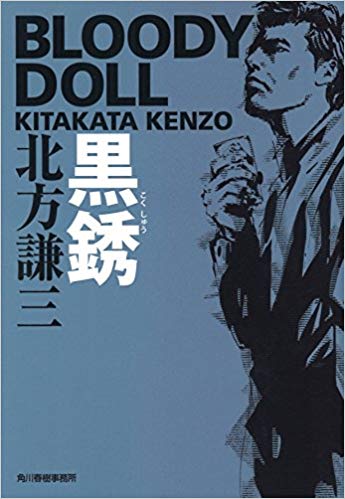
黒銹 こくしゅう
“ブラディ・ドール”シリーズ 5
獲物を追って、この街にやってきた。
そいつの人生に幕を引いてやる、それが仕事のはずだった。
妙に気になるあの男と出会うまでは──
惚れた女がやりたいと思うことを、やらせてやりたい──
たとえ、それが自分への裏切りだとしても──
あの男はそういって銃口に立ちふさがった。
それが優しさ?
それが愛ってもんなのか?
私を変えたあの日、裏切りを許せなかった遠い過去が心に疼く。
殺し屋とピアニスト、危険な色を帯びて男の人生が交差する。
ジャズの調べに乗せて贈る“ブラディ・ドール”シリーズ、第五弾。
“ブラディ・ドール”シリーズ 5
獲物を追って、この街にやってきた。
そいつの人生に幕を引いてやる、それが仕事のはずだった。
妙に気になるあの男と出会うまでは──
惚れた女がやりたいと思うことを、やらせてやりたい──
たとえ、それが自分への裏切りだとしても──
あの男はそういって銃口に立ちふさがった。
それが優しさ?
それが愛ってもんなのか?
私を変えたあの日、裏切りを許せなかった遠い過去が心に疼く。
殺し屋とピアニスト、危険な色を帯びて男の人生が交差する。
ジャズの調べに乗せて贈る“ブラディ・ドール”シリーズ、第五弾。
<単行本>1988年4月 刊行
<文庫本>平成3年3月25日 初版発行
ピアノ
耳が、なにかを思い出していた。
私は、入口のポスターの前で一度立ち止まってから、店の中に入った。
ボーイが近づいてくる。
きちんとした態度だった。
カウンターの方を、私はちょっと指でさした
頷いて、ボーイが先導する。
女の数も、かなりいる店のようだ。
ボックス席はほぼ埋まっていて、カウンターにも二人の客がいる。
「ジン・トニック。ソーダとトニックのハーフ・アンド・ハーフで」
前に立って頭を下げたバーテンに、私はそう註文した。
「ジンは、なんにいたしましょうか?」
「ゴードンだけがジンさ」
バーテンが、ちょっと口もとを綻ばせた。
タンカレーやビーフィターというような、流行りのジンも、酒棚には並んでいる。
まだ若いが、バーテンはいい腕をしていた。
ソーダとトニックウォーターを同時に注ぎこんで、ほとんど攪拌の必要がないように仕上げている。
あまり掻き回すと、ソーダが死ぬ。
甘いジン・トニックになってしまうのだ。
客が、自分の好みに合わせて、マドラーで掻き回すべきだった。
黙って、私はコリントグラスを口に運んだ。
ピアノ・ソロ。
十五年も前に聴いた曲。
あのころより、どこかに錆が浮いたような演奏だった。
それが、悪くない味になっている。
「あのピアニスト、長いのかね?」
「おえ。昨年のクリスマスからです。まだひと月にもなっておりません」
「毎晩、やるのか?」
「いまのところ、そういう予定でございます」
「いつも、ジャズだね」
「いいえ。お客様の好みに合わせて、映画音楽などもこなします。
すべてとは言いきれませんが、知っている曲ならば、やってくれます」
ちょっと頷いて、私はシガリロに火をつけた。
シガーやシガリロは、他人に火を出されると迷惑な気分になる。
自分なりの火のつけ方があって、それを変えたくないのだ。
特にシガーはそうだろう。
若いバーテンは、それをちゃんと心得ているようだった。
曲が、『ひまわり』になった。
鮮やかなひまわり畠の中を、女がひとり歩いていく。
映画のその場面だけをはっきり憶えていた。
...続きは本書でどうぞ
耳が、なにかを思い出していた。
私は、入口のポスターの前で一度立ち止まってから、店の中に入った。
ボーイが近づいてくる。
きちんとした態度だった。
カウンターの方を、私はちょっと指でさした
頷いて、ボーイが先導する。
女の数も、かなりいる店のようだ。
ボックス席はほぼ埋まっていて、カウンターにも二人の客がいる。
「ジン・トニック。ソーダとトニックのハーフ・アンド・ハーフで」
前に立って頭を下げたバーテンに、私はそう註文した。
「ジンは、なんにいたしましょうか?」
「ゴードンだけがジンさ」
バーテンが、ちょっと口もとを綻ばせた。
タンカレーやビーフィターというような、流行りのジンも、酒棚には並んでいる。
まだ若いが、バーテンはいい腕をしていた。
ソーダとトニックウォーターを同時に注ぎこんで、ほとんど攪拌の必要がないように仕上げている。
あまり掻き回すと、ソーダが死ぬ。
甘いジン・トニックになってしまうのだ。
客が、自分の好みに合わせて、マドラーで掻き回すべきだった。
黙って、私はコリントグラスを口に運んだ。
ピアノ・ソロ。
十五年も前に聴いた曲。
あのころより、どこかに錆が浮いたような演奏だった。
それが、悪くない味になっている。
「あのピアニスト、長いのかね?」
「おえ。昨年のクリスマスからです。まだひと月にもなっておりません」
「毎晩、やるのか?」
「いまのところ、そういう予定でございます」
「いつも、ジャズだね」
「いいえ。お客様の好みに合わせて、映画音楽などもこなします。
すべてとは言いきれませんが、知っている曲ならば、やってくれます」
ちょっと頷いて、私はシガリロに火をつけた。
シガーやシガリロは、他人に火を出されると迷惑な気分になる。
自分なりの火のつけ方があって、それを変えたくないのだ。
特にシガーはそうだろう。
若いバーテンは、それをちゃんと心得ているようだった。
曲が、『ひまわり』になった。
鮮やかなひまわり畠の中を、女がひとり歩いていく。
映画のその場面だけをはっきり憶えていた。
...続きは本書でどうぞ
