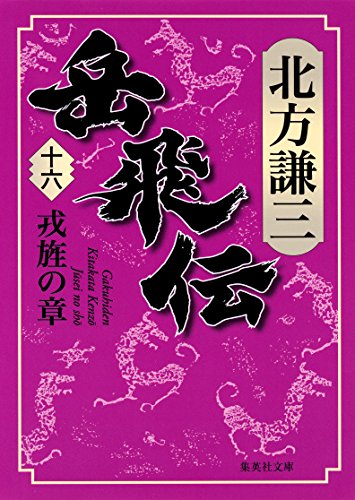
岳飛伝 十六
戎旌の章
中華全土が戦場と化していた。
沙門島沖では狄成と項充が、攻めてきた敵の海鰍船に忍び込み、船もろとも消失させた。
一方、海陵王は刺客を使い胡土児の暗殺を企てていた。
羅辰は、南宋水軍が南の甘蔗園を狙っていることを察知し、象山の造船所に火を放つ。
梁山泊軍は、姑息な手を使う海陵王に激怒し奇襲をかけた。
岳飛と秦容は、中原で死闘を繰り返している。
一つの中華を目指す忠肝義胆の第十六巻。
戎旌の章 目次
李師の火
地文の夢
天巧の光
韓海の火
天寿の光
戎旌の章
中華全土が戦場と化していた。
沙門島沖では狄成と項充が、攻めてきた敵の海鰍船に忍び込み、船もろとも消失させた。
一方、海陵王は刺客を使い胡土児の暗殺を企てていた。
羅辰は、南宋水軍が南の甘蔗園を狙っていることを察知し、象山の造船所に火を放つ。
梁山泊軍は、姑息な手を使う海陵王に激怒し奇襲をかけた。
岳飛と秦容は、中原で死闘を繰り返している。
一つの中華を目指す忠肝義胆の第十六巻。
戎旌の章 目次
李師の火
地文の夢
天巧の光
韓海の火
天寿の光
李師の火
茸を干したものを、ひと晩水に浸け、滲み出してきた汁を煮つめる。
それは一日分で、数回に分け、湯で割って飲む。
さまざまな薬湯を飲んだが、それが最も効くと秦檜は感じていた。
茸は三種類で、昨年の秋に大量に採ったものを、高い床の倉に置いてある。
籠で二十ほどだという。
寝ついているわけではない。
宰相府の執務室では、桂姸がそれを作るし、万波亭では王妙が出す。
秦檜は茶を飲むように、息を吹きかけながら啜るのである。
もともとは、桂姸の故郷の山で、やっていることだったらしい。
木の根に生えているような茸ではなく、崖に育って、捜すのも採るのも命がけだという。
戦に、進展はなかった。大きなところでは二カ所、国内に敵がいる。
全体から見ると点のような病巣だが、見えない病巣はじわりと全国に拡がっている。
程雲は、地方軍の編制をやり直し、守備だけでなく、攻撃もできる軍に変えようとしていた。
それができれば、兵力で敵を圧倒するだけでなく、叛乱をひとつずつ、徹底して叩き潰せる。
叛乱の対処をきちんとして、戦に臨もうという程雲のやり方を、秦檜は認めていた。
岳飛を、討ちもらした。
きわどいところで討ちもらし、一度は、生死の境まで追いこんだ。
そこまで行くと、運としか言いようがない。
程雲は腰を据えて構え直し、もう一度、自分の運を賭ければいいのだ。
茸の汁を啜っていると、臨安府で桐和と細かい話し合いをするために、雷州から来ていた薛崇が、汗を拭いながら現われた。
まだ、暑い季節ではない。
多分、大量の食い物を腹に詰めこんだのだ。
「御報告だけ、よろしいでしょうか」
「言ってみよ」
「一応の、細い道筋はできあがりました。兵站部隊が遣えるそうです。
輜重十輛に、護衛が二百。それが十隊です」
「兵站部隊の許可は はじめから出してある」
「雷州までの道筋が、確保できたということであります、宰相。
いくつかの城郭に岳飛軍が入っていて、戦時となるとそれが邪魔だったのです」
絹織物の移送は、戦時でも途絶えさせたくなかった。
そのための兵站部隊だが、轟交賈の二倍以上の費用がかかる。
そして、兵站部隊さえ出動すればいいという、単純なものでもないらしい。
秦檜はただ、絹織物が作られ、雷州に集まり、それがどこかへ運ばれていく、ということだけを重視した。
細かいことは、部下がやればいいのだ。
雷州の守備は、万全のはずだった。
それに、産物を襲ったりはしないという暗黙了解が、いまのところ梁山泊との間にはあった。
夏悦の船隊は、南にいる。
それがいずれ象の河に達すれば、甘蔗園を襲うということになる。
その時に、解は崩れるだろう。
いや、夏悦の船隊の四十艘ほどは、日本にむかった。
それを知った梁山泊水軍が、船隊を止めようとする。
そこで行われる海戦で、梁山泊水軍の船は、かなり減らせるはずだった。
しかし四十艘は、消息を断っている。
一艘も、戻ってきていないのだ。
そこで、自分は、誤りを犯したのか。
昆布を押さえるために船隊を派遣するというのは、自分の命令で、海戦を覚悟しないかぎり無理だ、と夏悦は言った。
昆布が欲しい。
甘蔗糖も欲しい。
そして、絹織物はすでにある。
南宋は、物産の国であるべきだった。
その三つを手にすれば、交易では絶対的な力を持てる。
それは、轟交賈を自らの懐にとりこむことでもあった。
しかし、見果てぬ夢なのか。
物産と物流を手にするということは、ほとんどすべてを手に入れるということではないか。
なにか 欲望のようなものが、夏の雲のように心に湧きあがってきたのは、自らが病を得ていると自覚してからだった。
それは、死を自覚してからでもある。
「薛崇、民はしばらく苦しい思いをするだろう。
しかし、戦はいつまでも続かぬ。続けられるわけがない。
疲弊だけが残り、勝者などおるまいよ」
「しかし、宰相」
「そうだ。負けはせぬが、勝てもせぬ。そういう戦なのだ。 勝負は、戦のあとということになる。 富が、優劣を決めるのだ」
「言われている意味は、わかるような気がいたします。それでも、私は勝たなければならない、と思います」
「そうだな」
秦檜は、茸の汁を啜った。
銀は蓄えるものではなく、生み出すものだ。
それができているかどうかが、戦後の勝負になるのだ。
桐和も薛崇も、そのために働いている。
戦に勝者などいないと、最初に見きわめたのは、梁山泊ではないのだろうか。
旧宋と 闘い 続けてきた。
宋を倒しても 国らし 国を作ある地域を、自分たちの領分のようにして、交易の手を方々にのばした。
戦に勝者などいないという考えどころか、これまでの国の姿など、形骸にすぎない、という考えに到ったのではないのか。
動きを見ていると、これと指させる国に、大きな関心を持っているとは思えないのだ。
それなら自分は、ただ形骸である国を 守ろうとしているだけなのか。
なにもかも欲しい。
そう思いながら、こういうことも考えてしまう。
自分が、早晩死ぬと思うようになってからは、常にそうだった。
「桐和殿との話し合いで、宰相にお願いしなければならないことが出てきまし た」
秦檜は、軽く頷いた。
「備蓄してある米を、ある程度出していただきたいのです」
米を買い集めていたのは、間違いなく梁山泊だろう。
その米を戦の手段のひとつとして遣わせないためには、こちらも米を持っていなければならない。
黄広は、いまだ大規模な隠匿を摘発していない。
よほど巧妙な隠し方をしてあるのだろう。
しかし、岳飛にも秦容にも、兵站として米は届いている。
軍の兵糧は、地方軍を含めて充分だった。備荒用としての米も、かなりある。
「隠匿された米に対抗するために、備蓄の米が必要であることは わかっておりますが 絹の生産を絶やさないためには、銭ではなく米で払ってやらなくてはならない情況が、来ると思います。
「わかった」
秦檜は、短く言った。
物流は、 すでに半分近く止まっている。 やがて、米はあるかなきかになるだろう。
「岳飛のやつ」
呟いた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
