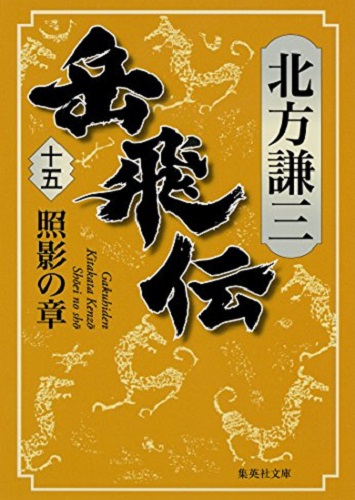
岳飛伝 十五
照影の章
狙うは、岳飛の首。
しばらくの間、人夫となって潜伏していた南宋の程雲は、ついに岳飛に奇襲をかけた。
岳飛は重傷を負い辛くも一命を取り留めたが、その際、程雲も負傷。
そして岳飛と呼応し東進する秦容軍は快進撃を続けていた。
梁山泊軍の呼延凌は、金軍との全軍対決に向け、準備を整えつつあった。
一方、南宋で秦檜の病が深刻な事態となっていた――。
三つ巴の最終決戦前夜、機略縦横の第十五巻。
照影の章 目次
瓊母の風
麻泚の火
山奇の風
地陰の夢
地満の夢
照影の章
狙うは、岳飛の首。
しばらくの間、人夫となって潜伏していた南宋の程雲は、ついに岳飛に奇襲をかけた。
岳飛は重傷を負い辛くも一命を取り留めたが、その際、程雲も負傷。
そして岳飛と呼応し東進する秦容軍は快進撃を続けていた。
梁山泊軍の呼延凌は、金軍との全軍対決に向け、準備を整えつつあった。
一方、南宋で秦檜の病が深刻な事態となっていた――。
三つ巴の最終決戦前夜、機略縦横の第十五巻。
照影の章 目次
瓊母の風
麻泚の火
山奇の風
地陰の夢
地満の夢
瓊母の風
船には、配船というものがある。
一艘の大型船が、十三湊で昆布を積んで出発する。
南の島伝いの航路の、最も大きな補給地でそれを降ろし、甘蔗糖の樽を積んで、再び十三湊にむかう。
それなら、大型船が空船で動くことはない。
昆布と長江(揚子江)沿いの物品を交互に運んでも、空船ではない。
船の航程や積荷について、しっかりと頭に入っていて、どの船はどこ、と配船する者には、全体的な視野が必要になる。
そういう人間を、張朔は選びに選んで、いまは沙門島と補給地の島の二カ所に置いている。
それぞれ五名ずついて、十名ほどの部下を遣いながら、無駄なく荷と船を動かす。
それを変更するには、張朔といえども、事前の連絡と協議が必要だった。
でなければ、どこかで荷が滞り、空船が航走る。
長江を溯上する船に昆布を積み換えると、張朔は南宋の物品を満載して、補給地の島へ行った。
そこで荷を降ろすと、張朔の船はもう荷を積まない。
船倉に隔壁を入れて堅牢にし、船首に鉄の板を張ったり、甲板にもう一枚、板を載せたりする。
戦時艤装である。
兵員が、二百にもなるが、荷を積まない船内は広く、充分な余裕がある。
もう一艘も、同じようにしている。
中型船はもともと戦時艤装だが、乗っている者は、かなり入れ替る。
船に手を入れている間、張朔は陸上の営舎にいた。
島の集落があるところなどに行くことは禁じていて、歩き回れるのは営舎周辺である。
便船は、しばしばやってくる。
鳩の通信も試みられたが、距離がありすぎて駄目らしい。
それに海には、猛禽も少なくない。
群れている海鳥でも、鳩の数倍の大きさはあった。
営舎の一室で、配船の手配などをしている者たちは、いずれ水運も轟交賈の管轄になった時は、それを背負う者たちだ。
水軍というかたちで、輸送の担当もしてきた張朔は、どこか肌の合わないものを感じる。
戦友という言葉で表わせず、役人に近いと思ってしまうが、いずれはそういう者が中心になるのだろう。
船 に 乗り組む 者 たち は、 思い思い に 鍛練 を やっ て いる。
櫓手をやる者たちは、脚や腕を鍛えると同時に、湾の深いところに潜る。
長い時を潜っていて、それを日に数十回くり返すのだという。
もう駄目だという、ぎりぎりのところに達した時、死を乗り越えてしまうのが、潜る力と似ているのだ。
張 朔もたまにやってみるが、すぐれた櫓手の半分も潜っていられない。
そして、せいぜい五回である。
営舎のはずれで、飛礫の稽古はやった。
これは、心気を澄ませるためでもあった。
昔、沙門島で、父に飛礫を教えて貰ったことを思い出す。
島の気候は寒くなく、しかし南方のように暑くもない。
便船に乗って、五郎がやってきた。
「南宋の絹織物の動きが、止まっていましてね。
南宋水軍が自分たちで運んでいるようでもあるのです」
絹織物は、南宋の最も大きな物産に育ってきて、どこへでも売れる、という強味がある。
西遼の朝廷が相当な量を買い、西域に売った。
その輸送は轟交賈だが、半分以上は、あるところまで南宋の水軍がやったようだ。
「おい、絹織物を奪えとでも、聚義庁は言っているのか」
「まさか。いまじゃ、轟交賈の、大きな仕事のひとつですしね」
「梁山泊水軍の輸送力は、しばらく半減するぞ」
「わかっています」
五郎はもう、日本刀を腰には差さず、中華ふうの剣を佩いている。
南宋水軍の動きが、いま南に集中しつつある。
雷州の物資の集積地を守るという意味からも、南に重点を置くのは理解できる。
その理解の裏に、なにか隠されてはいないか。
聚義庁も張朔も、同じことを考えたのだった。
それから、致死軍の報告が入った。
数ははっきりしないが、相当数の中型船が、象山で密かに建造されている、というのだ。
南宋水軍が不足しているのは、大型船である。
海鰍船があるがすでに古すぎて、ほかのものも旧型である。
海に強い大型船が二艘しかないのは、ある時まで南宋が本気で水運を考えていなかった、ということだ。
五郎は、倉庫の物品の確認に来たのかもしれない。
十三湊の任務からは完全に解放され、ほっとしているに違いなかった。
十三湊には、王清が行った。
夕刻まで、五郎は二十五棟ある倉庫に潜りこんでいた。
簡易な食堂があり、島の日本人がそこで働いている。
炸と炒などという料理方法はなく、山羊や豚を焼くか煮る、魚を生で醬か、焼くか煮る。
それだけの単純なものだった。
量に、不足はない。
張朔は、船頭たちと食事をとり、営舎の部屋に戻った。
「総帥、よろしいですか?」
五郎が、酒の瓶を抱えてやってきた。
部屋には卓と椅子と寝台があるだけである。
卓と椅子を脇によけた。
日本人は、床に座るし、そこで寝る。
中華では地に寝るような感覚だが、日本の床はどこもきれいに磨いてあった。
瓶も椀も、五郎は床に置いた。
「この酒、北の方で引き合いが多いそうです。
寝かせてあるところが、いいのかな」
甘蔗の搾り滓から作った酒で、かなり強烈である。
張朔は水を加えたが、五郎はそのまま、ちびちびと飲んでいた。
北で喜ばれる酒であることは、張朔も知っている。
船で運ぶ時は、水用の樽に詰め直している。
揺れで、甕が割れてしまうのだ。
「これを、藤原のお館様のところに持っていった時は、飲んで顔を顰めておられました。
しかし、また運んでこいとの、お達しがありました」
「藤原秀衡殿が、中華に来るということは、無理だろうな。北の王であるし」
「長く平泉をあけられるのは、やはり無理でしょうね。
窮屈な立場におられると思います。
十三湊にまで来られるのが、やっとというところでしょう」
五郎が、どこの者に命を狙われているのか、一度訊いたが、よくわからなかった。
あえて知ろうという気もない。
「李俊殿が沙門島を奪回された時、源太が活躍したのだと申し上げると、喜んでおられましたが」
戦が終ったら、平泉というところを訪ねてみようか、と張朔は思った。
十三湊にある中型船は、もうすっかり古くなってしまっている。
修理の方法などは教えているはずだが、あまり職人は育っていないようだ。
巨大な樹の幹を刳り貫いて船にする、と秀衡は最初は考えていた。
「源太の息子がいたな」
孫二娘が、孫としてかわいがっていた男の子だ。
いまは、本寨の学問所にいるはずだった。
「総帥は、源太の息子が、日本との繫がりになればいい、と思っておられますか?」
「ちょっとだけ、それを考えたことがある。 考えてみれば、中華で生まれ育った人間だ。 いまは、王清がいる。子供も生まれるだろうと思う」
「王清か。 王貴殿の兄弟ですよね。 俺 は、 十三湊で会っただけですが。聚義庁を見たって、ほかを見たって、俺などもう老人ですね」
「言うなよ、五郎。 俺の母は、おまえがいてくれて、ずいぶん助かったはずだよ」
それにはなんの反応もせず、五郎は椀を呷った。
(…この続きは本書にてどうぞ)
