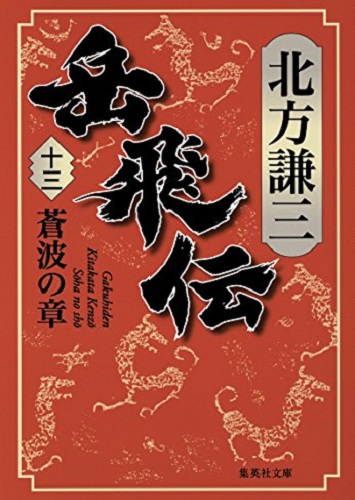
岳飛伝 十三
蒼波の章
奇策・霞作戦で挑んできた辛晃だったが、岳飛は高山兵を遣って景ろうを奪取した。
劣勢の辛晃軍は、梁岳道を突くが、秦容と岳飛に阻まれ敗走。
南宋の太子暗殺計画を知った燕青は李師師の元に向かうが、自身は深手を負い、彼女は既に毒に冒されていた。
梁山泊水軍の李俊は、南宋の手に落ちた沙門島の奪回に成功する。
金国の海陵王は、大軍で子午山を挑発し、史進の逆鱗に触れ――。
生滅流転の第十三巻。
蒼波の章 目次
青湖の風
地毛の夢
律石の火
地暴の光
劉世の火
蒼波の章
奇策・霞作戦で挑んできた辛晃だったが、岳飛は高山兵を遣って景ろうを奪取した。
劣勢の辛晃軍は、梁岳道を突くが、秦容と岳飛に阻まれ敗走。
南宋の太子暗殺計画を知った燕青は李師師の元に向かうが、自身は深手を負い、彼女は既に毒に冒されていた。
梁山泊水軍の李俊は、南宋の手に落ちた沙門島の奪回に成功する。
金国の海陵王は、大軍で子午山を挑発し、史進の逆鱗に触れ――。
生滅流転の第十三巻。
蒼波の章 目次
青湖の風
地毛の夢
律石の火
地暴の光
劉世の火
青湖の風
西への旅に、牛直はすっかり馴れた。
そこの物品を買い、中華の物を売る。
西の物品は旅で購い、中華の物品は轟交賈に註文を入れる。
楡柳館から西への、交易隊の差配が、牛直の仕事だった。
西の、さらに西へ行けば、海があるという。
それは中華を東へ横断してぶつかる海より、遥かに近いようだった。
交易隊という仕事がなければ、とうに行っているだろう。
その海のむこうに、なにがあるのか、いやでも考える。
東の海を見てもそう思うが、日本などの大きな島があることは、すでにわかっていた。
この大地は、どんなふうになっているのか。
それをきわめた者はいるのか。
西では、金色の髪も碧眼も、めずらしくなかった。
楡柳館にも、時折、そういう商人がやってくる。
「ただいま帰りました、牛直殿」
書類に署名をしている時、部屋の入口に韓順が現われて言った。
しばらく、土里緒の集落に行っていたのだ。
韓成は、息子がひとりでこちらにやってくるようになってから、あまり父と子の時を作らない、と決めていると言った。
理由は言わなかったが、冷たくあしらっているのではないことは、見ていてわかった。
できるだけ多くのことを、体験させようとしているのだ。
虎思斡耳朶からこちらへ来ても、西部方面総監の営舎にいるのは一日だけで、すぐに楡柳館へやってくるのだった。
土里緒の集落にかぎらず、楡柳館からいろいろなところへ出かけていく。
韓順を見るたびに、自分が武松に拾われたころのことを、牛直は思い出す。
「毛皮は脱げ、韓順」
到着してすぐに、報告に来たのだろう。
毛皮を二枚、着こんでいる。
冬になっていた。
山なみの雪は、いつもの年と変らず、轟交賈の輸送隊も、しばし 難渋するようだった。
山の雪ほどこちらはひどくないが、それでも膝が没するほどはある。
「土里緒殿は、お変りないか?」
「はい。白髪が増えたと嘆いておられますが、それは父も同じです」
楡柳館の建物には、石炭を燃やす炉がいくつか作られていて、煙は床下を通って屋根へ出る。
だからいつも、暖かかった。
以前は薪を燃やしていたが、それほど遠くないところに、石炭の鉱脈が見つかったのだ。
石炭を買うことで、鉱山の周辺の集落は、豊かになっている。
ここで燃やすのは、ほんの一部だった。
あとは骸炭(コークス)にして、湖の北側に船で運んでいる。
「金国の情勢を気にされていて、虎思斡耳朶に、しばしば人をやっておられます。
私も、虎思斡耳朶に戻ったら、わかったことはすべて飛脚で知らせろ、と言われました」
「金国は、俺も気になる。ここでわかったことは、土里緒殿に知らせよう」
帝が、海陵王になっている。
先帝の崩御は、それほど大々的には告知されなかった。
都も、会寧府から燕京(北京)に移っている。
「西 から 運ん で き た 品物 が、 倉 に ある。
明日、見に行こうか。今日、お父上に顔を見せてやれ」
「はい、そうします」
自分に最初に挨拶に来たのは、韓成にそう言われているからだろう。
供もつけず、ひとり旅をさせる。
しかも、雪である。
「二日前に、お父上に会った。きわめてお元気であった」
「父は、あれで憎らしいほど強いのだ、と土里緒殿はいつも言っておられます」
「憎らしいほどか」
牛直が笑うと、韓順も微笑んだ。
「馬は、 大丈夫なのか?」
「はい。望天は私の友で、雪の中を進むことも知っています 危険なところでは、必ず停まるのですから」
望天というのが、馬の名前だということは、聞いていた。それが、父親のあだ名だということも、この間、知った。
友と言われても、牛直には、ただいい馬としか見えなかった。
「中華の物品も、見たいと言っていたな」
「見たいと思います、ぜひ」
「まあ、西の物の方が、目新しいだろう。はじめに、それを見てからだ」
虎思斡耳朶の宮殿は、質素だが、それなりの品物は置いてあり、韓順はそれを見て育っている。
それは、大きなことだった。
どういうものが、儲かるのか。
それを牛直に教えてくれたのは、盛栄だった。
なぜ 価値があり、人が欲しがるのかは、上青が教えてくれた。
韓順が一礼して去っていくと、牛直はすぐには書類に戻らず、上青のことを思い浮かべた。
昔は肥っていて、堂々とした体軀だったような気がするが、思い浮かぶのは瘦せてしまってからの上青だった。
病が篤くなった上青に、牛直は寝台のそばに立って、毎月、報告をした。
この楡柳館の主は、長い間、上青だった。
つまり、牛直にとっては、隊長だったのだ。
死が近くなったころ、上青はいつも眠っている、というようにしか牛直には思えなかった。
なんの反応がなくても、牛直は報告を続けた。
あの報告を、上青はすべて聞いていたのだ。
上青の死に際を思い出すと、涙が出てくる。
牛直は、ようやく書類に眼を戻した。
王貴を頂点にした、梁山泊交易隊が、轟交賈に替ったというだけで、楡柳館の仕事の質はそれほど変っていない。
ただ、規模は大きくなった。さらに牛直自身が、西へ出かけるようになった。
それまでは、碧眼の商人が、楡柳館に物を売りに来たりしていたのだ。
旅をしてわかることだが、平和なところはどこにもない。
一見、なに事も起きていなくても、裏には憎悪や反目や利害の対立が、底流のようにしてある。
富んでいる国もあれば、貧しい国もある。
果ての果てまでは、まだ行っていない、という気持がある。
いま、韓順に頼まれているのが、西の旅へ同行させてくれ、ということだった。
自分が望んだ旅ができて、さまざまな体験もできる。
そういう星のもとに生まれてきた人間もいるのだと、韓順を見ているとしみじみ思った。
牛直は、盛栄と旅ばかりしていたが、そこには必ず物品が伴っていた。
行きたいと思っても、商いに関係がなければ、行くことはできなかった。
だから、商いとは関係なく、韓順にはさまざまなものを見せたいと思う。
そうやって見たことが、多分、国を造ったり変えたりする力になる。
(…この続きは本書にてどうぞ)
