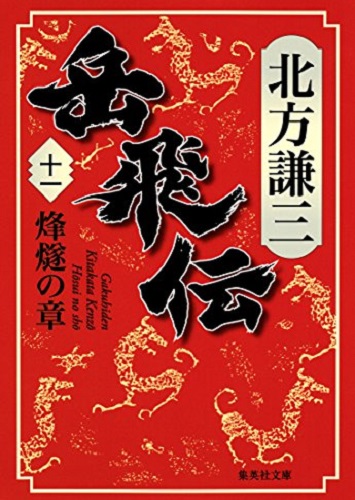
岳飛伝 十一
烽燧の章
七星鞭が吼え、胡土児が宙天に翻る。
梁山泊軍と金軍は今、最終決戦の時を迎えようとしていた。
米の不審な流れを追っていた南宋が陣家村を殱滅させた。
致死軍に救出された蕭けん材は、小梁山から金国にいたる広大な大地に、国の垣根を超えた物流網を整備していく。
一方、北に蒙古という強敵の姿も見え始めていた。
岳飛は南宋に残った臣下達との邂逅を果たす。
新たな時代の胎動を予感させる第十一巻。
烽燧の章 目次
粘切の火
地稽の夢
地祐の夢
葉舟の火
白鵺の風
烽燧の章
七星鞭が吼え、胡土児が宙天に翻る。
梁山泊軍と金軍は今、最終決戦の時を迎えようとしていた。
米の不審な流れを追っていた南宋が陣家村を殱滅させた。
致死軍に救出された蕭けん材は、小梁山から金国にいたる広大な大地に、国の垣根を超えた物流網を整備していく。
一方、北に蒙古という強敵の姿も見え始めていた。
岳飛は南宋に残った臣下達との邂逅を果たす。
新たな時代の胎動を予感させる第十一巻。
烽燧の章 目次
粘切の火
地稽の夢
地祐の夢
葉舟の火
白鵺の風
粘切の火
樹々の間を縫って、道を作った。
人ひとりが、ようやく通れるような小径である。
館から三本、そういう小径を十里(約五キロ)ほどのばした。
その間に、人は住んでいない。
人が通ったという跡すらなかった。
ほかと較べると、人が通るのが難しくないところだった。
崖や谷を避ければ、そのその三本しか小径は作れなかった。
梁紅玉は、三本の小径を自分の脚で歩いて、なんとなく安堵感を持った。
館は、間違いなく人里から隔絶された場所にある。
湾の南北十里の海岸にも、集落はないという。
館のそばに、部下たちは営舎を建てた。
倉もひとつ建てられている。
大型船の交易品を、日本の品物と交換したほかに、かなりの銀が手に入っていた。
荒々しく見えるが、炳成世はそこのところはきちんとしていた。
中型船二艘を、西へ偵察に出していた。
それには、炳成世のところの若い者が、十名ずつ乗っている。
もうすぐ、 戻ってくるはずだった。
ほかに預かっている三十名は、湾 中で操船の稽古をしている。
炳成世がどういう人間なのか、しばしば考えた。
手下が多い。
その手下が示す忠誠心のようなものが、尋常ではない。
それに、 梁紅玉が知っているどの男より、構えが大きかった。
ずっと先を見据えている、という気がする。
ただ、 五十名の手下と十艘の小舟を残しただけで、あれから姿を見せていない。
虎符と呼ばれる漢人の男は残されていたので、手下たちと話すのに不便はなかった。
交易船に乗っていて海賊に捕われた商人ということ以外、虎符は自分のことを語ろうとせず、炳成世の話題も出さなかった。
梁紅玉が訊いても、 答えない。
ほんとうのところは知らないのではないかと思え、ただ畏怖だけは大きく抱いているようだ。
浜には船着場が竹と木で作られ、潮が満ちた時には、中型船を二艘、繫げられる。
「帰ってきました」
小径を駈け降りてきた部下が、大声で叫んでいた。
小径の行き止まりには、小さな小屋が建ててあり、部下二人と炳成世の手下がひとり、交替で見張りに立っている。
ひとつの小屋からは、山の斜面だけでなく、湾の沖の海も見渡せるのだった。
やがて、二艘が湾に入ってきた。
館からそれを見ていた梁紅玉は、浜まで降りた。
満潮まであと二刻(一時間)というところで、中型船は難なく船着場に着けられた。
大きな報告は、南宋水軍が梁山泊水軍と激しい交戦をし、敗北して大打撃を蒙ったというものだった。
韓世忠が無事だったのかどうか、梁紅玉は気にしなかったが、生きていると部下は報告してきた。
南宋水軍の潰滅は、部下たちに大きな動揺を与えている。
「われらは、交易船隊なのです。
宰相からも、直々に命じられています。
この地で、交易をなします。
そして銀を蓄え、やがてそれを南宋に運びます。
われらの船が失われたわけではない。
われらは定海を出発した時のままの姿で、そして交易をはじめています。
梁山泊水軍に遭遇しないようにしていれば、戦の外にいられるということです」
二百名全員を集めて、梁紅玉は言った。
ひとりとして、若い兵はいない。
戦からははずれたが、航海では役に立つ、という者たちばかりだ。
最も年長の船頭は、六十歳を超えていた。
「この船隊が戦に加わることは、宰相も望んでおられません。
南宋水軍本隊でさえ、大敗したのですから。
この船隊の使命は、どこまでも交易です。
南宋水軍本隊が潰滅した以上、あらゆる方法で梁山泊水軍を避けながら、交易をなすし ありません」
部下たちから、 声はあがらない。
頷いている者が、数人見えるだけだ。
「この地は、梁山泊の交易水路からは大きくはずれています。
ここを全船隊の船溜りとし、船の手入れなどを行い、乗員の休息や調練などもまた」
「隊長。交易の相手は、どこになるのでしょうか?」
年長の船頭が言った。
「炳成世殿と、南宋、及び金 国。その物産などを運び、銀 を得ます」
全員が、大きな危険はないと理解したようだった。
「生き延びるために、無理なこともしてきました。これから先は、糧食も購えます。何年か経てば、国へ帰る道も見えてくると思います」
水夫たちが、国へ帰ることを切望している、というところはなかった。
水軍にいる者も、陸上の軍にいる者も、一生のうちに故郷へ帰れれば、無上の喜びだと思っている。
そうやって帰った者も、故郷では忘れられていたりするのだ。
「この地を、私は故郷とします。二番目の故郷」
一番目の故郷である無為軍(郡)の造船所は、戦で焼かれてしまっているという。
部下は、密かに中華に上陸し、市まで行ってさまざまなものも買い集めてきた。
中型船なのでたいした量では いが 陶器、磁器がひと箱ずつあり、絹織物や日本ではめずらしい文具、薬、香料などがあった。
「米を買い占めて、高値で売った商人たちが摘発されたようです。危険だと思ったので、詳しくは訊きませんでした。品物は、多いと感じました」
炳成世の手下も四名上陸していて、市などを見てきたらしい。
しかし、 梁紅玉に報告するということはなかった。
銀の小袋を持たせていたが、手付かずだった。
よく数えてみると、袋がひとつ多い。
真珠十粒が、それだけで売れたということだ。
宝石や貴石に近い価値が、もしかするとあるのかもしれない。
炳成世が現われたのは三日後で、早すぎると梁紅玉は思った。
なにかしら、連絡を受ける方法を、持っているのかもしれない。
上陸した四名は、並んで片膝をつき、炳成世に報告しはじめた。
炳成世以外には報告しない、というような態度に見える。
「偵察と言いながら、いい商いができたようだな、梁紅玉殿」
炳成世が闊達に言った。
高貴というのではないが、多くの人間の上に立っているのは間違いない。
「大型船を出して、もっと大がかりにやりますか、炳成世殿」
「慌てるな。 むこうで、同心してくれる商人を二人ばかり捜そう。
多少の利を与えれば、喜んでやる人間がいるだろう。
その二人を見つけるためには、梁紅玉、おまえが行ってくれないか」
「大型船を出すのなら」
「いや、中型二艘だ。物を運ぶのではなく、まず人を捜すのだ」
「炳成世殿、真珠がいい値で売れます」
「わかってるさ。十粒で、おまえらの銀を遣わなくても済んだだろう」
(…この続きは本書にてどうぞ)
