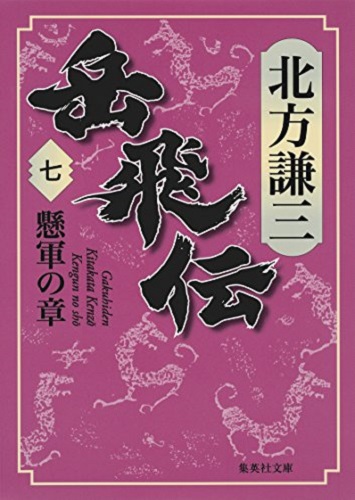
岳飛伝 七
懸軍の章
南宋の根本を揺るがす「印璽・短剣」と引き換えに、秘密裏に南宋を脱出した岳飛。
直後、許礼ら南宋軍に追われるも、梁山泊の致死軍に守られ南下、大理の近くで居を構えることに。
そんな中、弱体化したかに思われた青蓮寺の不穏な気配が其処彼処で感じられるようになる。
一方、秦容のいる南の開墾地は銭が流通し、町としての機能が整い始めていた―。
独り聳立する岳飛。
ついに岳家軍、再起の第七巻。
転遠の章 目次
炳杳の火
鄔老の火
地退の夢
離不の火
天剣の夢
懸軍の章
南宋の根本を揺るがす「印璽・短剣」と引き換えに、秘密裏に南宋を脱出した岳飛。
直後、許礼ら南宋軍に追われるも、梁山泊の致死軍に守られ南下、大理の近くで居を構えることに。
そんな中、弱体化したかに思われた青蓮寺の不穏な気配が其処彼処で感じられるようになる。
一方、秦容のいる南の開墾地は銭が流通し、町としての機能が整い始めていた―。
独り聳立する岳飛。
ついに岳家軍、再起の第七巻。
転遠の章 目次
炳杳の火
鄔老の火
地退の夢
離不の火
天剣の夢
炳杳の火
岳州にむかっていた。
褚律の歩き方は、人が走るのより速い。
梁山泊に来てから身につけたものだが、躰を鍛えてさえあれば、極端に難しいというものではなかった。
周囲の気配には、注意を払っていた。
人がいるところでは、歩調を落とす。
岳州陳家村を訪れ、柴健に会ってきた者たちから、村の微妙な変化を伝えられていた。
気にするほどではないという判断を一応は下したが、ひっかかるものはあった。
褚律は、岳飛と姚平の旅を見守って、大理との国境まで行った。
できるかぎり、手は出すなと、燕青からは言われていた。
しかし、二人が襲撃を受け、危ないと思った時、介入していた。
姚平を担いだ岳飛を逃がしたが、顔は見られた。
岳飛が病に倒れたりして、大理までは思わぬ日にちがかかった。
それに、岳飛は悠然としていて、急ぐようではなかったのだ。
二人を襲ったのが何者なのか、調べることは難しかった。
撤収する時、仲間の屍体も担いでいったのだ。
ただ、臭うものはあった。
集団での動きの連携はとれていた。
しかし、争闘を主とする者たちではない。
潜入や攪乱などを任務とする部隊だと思えた。
その臭いは、なぜか褚律に青蓮寺を思い起こさせた。
青蓮寺については、直接闘ったことはあまりない。
だから、どういうものだというのも 頭の中で決まってしまっていた。
思わず青蓮寺の臭いを嗅いだのは、燕青や侯真や羅辰の言葉が蘇ったからだろう。
臨安府の青蓮寺がどうなっていかは、じっくりと見ていた。
見れば見るほど、摑み難いものは出てきたが、梁山泊が警戒しなければならないものはない、と褚律は感じていた。
それは、羅辰の見方も同じだった。
青蓮寺の実際の動きが活発になったのは、岳飛が放免される時からだった。
秦檜の動きは、放免してのち、軍を動員して捕えようというものだった。
秦檜自身の意思とは思えない。
岳飛を捕えるために敷いた態勢は、戦を知っている者ではなく、頭で考えたとしか思えない硬直したものだった。
岳飛は、楽々と包囲を破り、南へむかった。
その移動の平然としたさまは、 追手の眼を見事にくらましていたし、褚律の心の底も、どこかで揺り動かした。
岳飛が病に倒れた時、褚律は右往左往している姚平をただ眺めていた。
弓疵(破傷風)らしく、 助かるのは難しいだろ う、と思った。
惜しいという気はしたが、病で潰えればそれだけのものだ、とも思った。
弓疵の発作を、数日耐えていた人間を、褚律は知らない。
大抵は、発作が数度で、絶息して死ぬ。
二日保つ者は、稀だった。
軽く済む人間が生き延びるが、それは発作が三度か四度程度なのだ。
岳飛は、数十度の発作に襲われ、それでも生き延びて、また平然と旅を続けていた。
大理に入ったのを見届けてから、褚律は気持にひっかかっていた、陳家村へむかっむかったのだった。
その途中で、羅辰の部下が、別の情報を届けてきた。
南宋の三カ所の土地で、銀の鉱脈が発見され、掘られはじめた。
昼夜兼行で、臨安府の手が入った時は、掘り尽されていたという。
つまり銀山の存在を臨安府は摑でおらず、どこかが密かに掘り、運び出せるようにしていた、とえる のがいいだろう、 という羅辰の判断もあった。
誰がそれを やっていたか、考えて出てくるは多くない。
青蓮寺と考えるべきだろう。まだ南の混乱期、李富が銀鉱を探させた。
そして、 見つけたものを秘匿していた。
それぐらいのことは、やる男だろう。
銀山の規模がどれほどのものかはわからないが、青蓮寺が、臨安府から独立した力を持ったと、頭には入れておいた方がいい。
燕青は、京兆府(長安 のあたりにいて、そこで南宋と金国の講和交渉を見守っていた。
少し日数はかかったが、講和は成った。
ともに、国内の動きは活発になったようだ。
梁山泊がそれにどう対応するのか、 その指示は聚義庁から届いていない。
届くまで、自分の判断で動くというのが、褚律のやり方になっていた。
「燕青殿」
岳州が近づいたころ、前方を歩いている人間の背に、褚律は声をかけた。
「見破られたのか。 私も未熟だ」
燕青は、旅芸人の恰好を変えていない。
笛吹きの老人である。
「陳家村へ、 行かれるつもりですか?」
「おまえの報告だけでなく、あそこへ行く理由ができた」
(…この続きは本書にてどうぞ)
