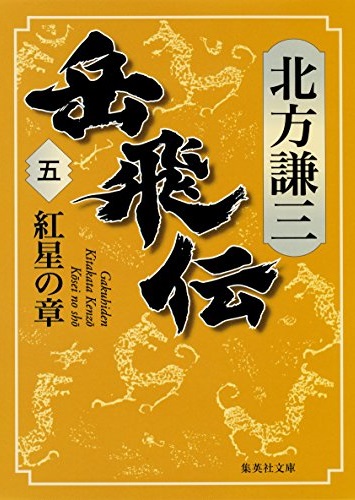
岳飛伝 五
紅星の章
南宋の宰相・秦桧は闇の中で戦いが終わってからのことを考えていた。
そんな中、梁山泊の宣凱が岳飛を訪ね対話をする。
岳飛は答えた。
「中華を中華の民の国にしたい」と。
一方、梁山泊の南の開墾地は本格的に始動。
戦場では南宋軍の岳飛と金国総帥・兀朮が互いを求め、渾身の力を込めた激闘を繰り返していた。
突然、秦桧から南宋軍に帰還命令が届く――。
岳飛の決断とは。
紅星の章 目次
九頭の宙
譲陽の火
響媛の宙
坤姚の光
天傷の夢
紅星の章
南宋の宰相・秦桧は闇の中で戦いが終わってからのことを考えていた。
そんな中、梁山泊の宣凱が岳飛を訪ね対話をする。
岳飛は答えた。
「中華を中華の民の国にしたい」と。
一方、梁山泊の南の開墾地は本格的に始動。
戦場では南宋軍の岳飛と金国総帥・兀朮が互いを求め、渾身の力を込めた激闘を繰り返していた。
突然、秦桧から南宋軍に帰還命令が届く――。
岳飛の決断とは。
紅星の章 目次
九頭の宙
譲陽の火
響媛の宙
坤姚の光
天傷の夢
九頭の宙
剣の稽古は、続けていた。
しかし、日頃は剣を佩くことはなかった。
邪魔になるし、拳を使う職掌でもない。
暇があれば、馬にも乗った。
父の宣賛は、史進の乱雲を見事に乗りこなしたという。
宣凱が荷崩れで大怪我をした時、父は乱雲で駆けつけてきたのだ。
馬の背にしがみつくだけだった父に、 乗馬を教えたのは、 林冲だったという。
林冲という、いまだある畏怖を持って語り継がれる豪傑が、 父に自ら乗馬を教えたというのが、 宣凱には不思議だった。
父の世代の、梁山泊のありようが、 いまひとつ宣凱には理解できない。
周囲に、 二十騎いた。
その後方に、さらに五十騎がいる。
呼延凌が、選びに選んだ警固の兵である。
警固は、それだけではないようだった。
方々に致死軍の兵がいるようで、それは先行していて、いつも宣凱を迎える恰好になる。
いま、自分が岳飛と会わなければならない理由は、 なにも見出せなかった。
呉用の、意思である。
呉用はまた、遺言だと言った。
最後の頼みだとも、命令だとも言った。
呉用がそれだけのことを言ったのは、 はじめてと言っていい。
これまで、意思表示のようなものはせず、宣凱が言ったことに、同意するか否定するかだけだったのだ。
呉用がいることが、宣凱にとっては救いだったが、時々、死ぬことはないのではないのか、という気分に襲われる。
もしそうなら、たまらなく煩わしい存在になる。
呉用がいなくなったらどうなるか、という想定は、飽きるほどくり返した。
いまはもう、それすらもやらなくなった。
呉用は、岳飛に会えと言っただけで、なにを話すかについては 一切なかった。
すべて自分に任されたことだ、と出発してからは思うようになった。
以前なら、理不尽とさえ感じただろう。
梁山泊の宣凱として、岳飛と話せばいいと思い、それ以上のことは考えず駈けてきた。
戦場として予測される場所を、大きく迂回してきた。
金国との講和はあるのだ から、どこにいてもいいようなものだが、なにしろ金国の戦相手の主力である、岳飛に会いにいくのだ。
岳飛に会うことについて、呼延凌は自分も一緒に行くと言った。
ひとりだけで行か行かせろと言ったのは、史進だった。
つまり二人とも、宣凱が岳飛に会うことは、当然のことのように認めたのだ。
「このあたりから、南宋軍の勢力範囲に入るそうです。
兵が蝟集している地域は避けますが、金軍の斥候とはすでに二度、遭遇しております」
警固の隊長である高亮が、そう言った。
岳飛軍の位置は、だいぶ前から把握しているようだった。
宣凱は、なにも訊かない。
岳飛の前に出た時から、自分の任務ははじまる。
百騎にも満たない騎馬隊について、斥候はその動きを見失わないようにしているだけで、それ以上大きく動く気配はなかった。
「あれが」
馬を停め、遠くの陣を指さして、高亮が言った。
本寨を出発して、四日目である。
南宋軍は、ずいぶんと北まで攻めのぼってきているのだ、と宣凱は思った。
大きく迂回して、南宋軍の背後に出ているのだと、高亮は説明した。
「これ以上近づくのが、難しいのです。
決して、捕えられたかたちで、宣凱殿を岳飛に会わせてはならない、と言われておりますので」
「誰に?」
「総帥からも、史進殿からも」
「わかっ た」
宣凱は、先頭に立ち、馬を進めはじめた。
高亮は慌てず、ただ馬を寄せて、宣凱の意思を確かめた。
「駈けこんでも、どこかでぶつかるでしょう。
梁山泊と名乗って、攻撃されることはないという気もしますが、確認に時を要すると思います。
私は急ぎ、帰らなければならないのです、高亮殿」
「しかし、ここをこの状態で突破するとなると」
「掲げてください。 あの旗です」
「えっ、そのために」
高亮は言ったが、命令には即座に従い、旗手に旗を掲げさせた。
『幻』の旗である。
その旗は、宣凱が自分の考えで持たせてきたものだ。
並足で進んだ。
黒地に幻の字の旗が、風に靡いて音を立てている。
岳飛軍の陣営に、明らかにそれとわかる動きがあった。
十騎ほどが飛び出してきた時、両側にも、近くにいたらしい斥候隊が三十騎ほど集まっていた。
十騎は、宣凱の前まで駈けてきて、停まった。
正面にいる大きな男が岳飛だろう、と宣凱は思った。
右腕がある。
それはいささか不思議だったが、岳飛に間違いはない、と確信できた。
岳飛は、旗をじっと見つめていた。
いくらか悲しげに見える視線は、いつまでも動かなかった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
