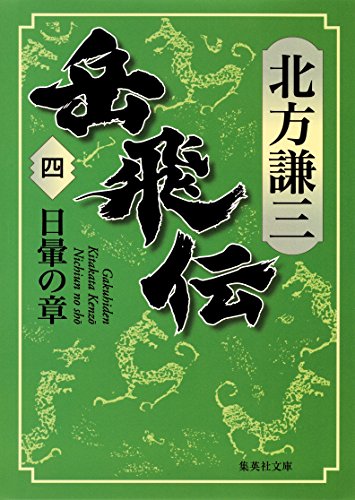
岳飛伝 四
日暈の章
ついに金国と南宋が激突!
兀朮率いる三十万の金軍が南下、南宋は岳飛軍、張俊軍などを併せ二十万で迎え撃つ。
緒戦から激しいぶつかりあいが続く。
金軍の沙歇が、張俊軍の辛晃が、戦場を縦横無尽に駈け回る。
胡土児も必死に兀朮を守り戦うが容赦ない攻めに難渋する。
岳飛はついに乾坤一擲の策を繰り出した。
一方、漢人による豊かな国を目指す秦檜の思惑は如何に――。
日暈の章 目次
徐女の宙
神箭の風
地理の光
紅天の宙
帥旗の火
日暈の章
ついに金国と南宋が激突!
兀朮率いる三十万の金軍が南下、南宋は岳飛軍、張俊軍などを併せ二十万で迎え撃つ。
緒戦から激しいぶつかりあいが続く。
金軍の沙歇が、張俊軍の辛晃が、戦場を縦横無尽に駈け回る。
胡土児も必死に兀朮を守り戦うが容赦ない攻めに難渋する。
岳飛はついに乾坤一擲の策を繰り出した。
一方、漢人による豊かな国を目指す秦檜の思惑は如何に――。
日暈の章 目次
徐女の宙
神箭の風
地理の光
紅天の宙
帥旗の火
徐女の宙
北の穀物が集められている。
いまは収穫期ではないので、税とは別に徴発されたものなのだろう。
途中でそれを抜き、どこかへ流すという真似をする将兵は、いないようだった。
兵站路は、しっかりした規律の中にある。
侯真は、当てがはずれた商人のような顔を作って、宿に戻ってきた。
市場でも、闇の商人の間でも、麦は見つからなかった。
通常の作柄だったので、大抵はどこかに余っているものだ。
それだけ、兵站は強力で、つまり金軍がこれからはじまる戦に、腰を入れていることの証左だった。
燕京(北京)の宿にも、商人の姿は少ない。
穀物がこれだけ燕京に集まりながら、商人があまりいないというのも異様ではあった。
致死軍は、以前のように、闇の中の戦をする軍ではなくなりつつある。
梁山泊と金軍の講和で、戦そのものがなくなりつつあるのだ。
情報収集や、細かい諜略などを、これからの任務にしていくしかないのだろう、と候真は考えていた。
中華には、梁山泊のほかに、金国と南宋という大国家が南北に位置し、睨み合っている。
強力な軍と交易の利を擁した梁山泊は、その二国に対するために、まず情報が必要なのだ。
情報さえ摑み切っていれば、その両国もこわくはない。
梁山泊より北は侯真が、南は羅辰が担当することにした。
いま、人員の補充を、聚義庁に求めてはいない。
かつては、梁山泊軍の中で最も兵の損傷が激しいと言われていたが、いまは、大して減ることはないのだ。
旧宋の青蓮寺が、ほぼ実体がないのに等しい存在になっている。
南宋は、青蓮寺のような闇の軍の力より、政庁でしっかりと指示を出せる情報網を大事にしているようだ。
青蓮寺の動きを微妙に感じることもあるが、決定的なところに出てくることはなかった。
金国の政庁は、いま燕京にあると思える。
宮殿は北の会寧府にあるが、帝をはじめ丞相や重立った文官は、燕京にいる。
会寧府の宮殿より、燕京の離宮の方が、ずっと壮大なものでもあった。
かつて、燕京を中心とする、燕雲十六州に、新しい国が建てられようとした。
耶律淳が帝であったから、ほとんど国はできていた、と考えてもいい。
旧遼禁軍の中枢の軍は、旧宋金軍と五分の闘いを展開した。
地の利ということを考えれば、旧遼禁軍の方が有利だった、という見方もある。
新国家の建国や、強力な軍同士のぶつかり合いが、一瞬にして幕を降ろしたのは、耶律淳の暗殺によってだった。
青蓮寺の手によるものだ。
公孫勝とともに、羅辰がそれを確認してきている。
動き出す前に潰れた国家だが、一度動きはじめていたら、かなりのものになっただろう。
蕭珪材を中心とする軍がいて、開明的と言われた帝がいる。
それだけで、旧宋とも旧遼とも、金国とも違う国家ができたであろうことは、想像に難くない。
そうなれば、中華の歴史は変わっただろうし、梁山泊のありようもまた、変わったはずだ。
侯真は、運ばせた酒を、ちびちびと飲みはじめた。
もう、四十歳になった。
武松や燕青と、楊令を探す北への旅をしたのは、どれほど前のことだったか。
あの旅で、さまざまなものを、骨の髄まで叩きこまれた。
それ以降の、致死軍の一員としての闘いは、あの旅と較べると、まだ穏やかなものだった。
あの旅は、死にそうで死なない、という日々がずっと続いたのだ。
こんなふうにして、酒を飲み続けていた男のことを、侯真は思い出した。
戴宋である。
いつも酒の匂いがし、ことごとく若い者を馬鹿にし、そして中華を統一して新国家を築くことを夢としていた。
その戴宋にとって、物流を力とする国家の構想は、わけのわからないものだったのだろう。
帝がいて、宰相がいて、強力な軍がいる。
それ以外に、どんな国の姿があるのだ、と考えていた。
梁山泊でも、かなりの人間たちがそう考えていたが、口に出して言っていたのは戴宋だけだった。
(…この続きは本書にてどうぞ)
