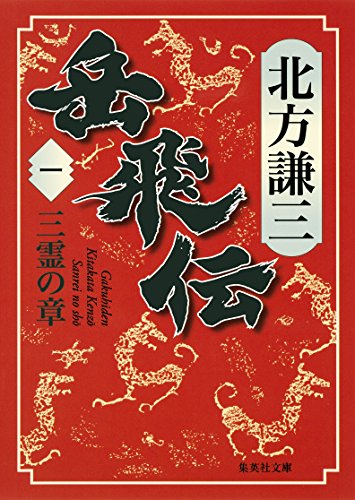
岳飛伝 一
三霊の章
負けたのだ。
「替天行道」と「盡忠報国」というふたつの志の激突だった。
半年前の梁山泊戦。
瀕死の状態の楊令に右腕を切り飛ばされた岳飛は、その敗戦から立ち直れずにいた。
頭領を失った梁山泊は洪水のために全てが壊滅状態にあった。
一方、金国では粘罕が病死した後、軍を掌握したのは兀朮。
そして青蓮寺が力を失った南宋も混沌とした状態だった。
十二世紀中国で、熱き血潮が滾る「岳飛伝」開幕!
三霊の章 目次
蒼天の風
地平の光
摸着の蒼
完骨の火
犴叩の風
三霊の章
負けたのだ。
「替天行道」と「盡忠報国」というふたつの志の激突だった。
半年前の梁山泊戦。
瀕死の状態の楊令に右腕を切り飛ばされた岳飛は、その敗戦から立ち直れずにいた。
頭領を失った梁山泊は洪水のために全てが壊滅状態にあった。
一方、金国では粘罕が病死した後、軍を掌握したのは兀朮。
そして青蓮寺が力を失った南宋も混沌とした状態だった。
十二世紀中国で、熱き血潮が滾る「岳飛伝」開幕!
三霊の章 目次
蒼天の風
地平の光
摸着の蒼
完骨の火
犴叩の風
蒼天の風
鉄笛だった。
その音色が、山士奇の心のどこかに、はっきりと残っていた。
吹いていた人間は二人だった、とシュウ聚義庁の階を降りながら、山士奇は思った。
馬麟と、張平である。
広場を歩いていくと、湧水のそばに、背中が一つ見えた。
ここの湧水は、周囲が水浸しになろうとなら枚と、同じように湧いては,賽外に流れだしている。
見知らぬ顔が、鉄笛を吹いていた。
山士気の気配がそうさせたのか、吹くのをやめ、顔をこちらにむけてきた。
「おまえは?」
「王清といいます。三刻ほど前に、ここに入りました。」
「梁山泊の人間か?」
そういう匂いはした。
しかし、兵ではない。
軍人が放つ、集団を感じる気配が、まるでないのだ。
「兄弟は、梁山泊の人間です。
兄、弟ではなく、双子の兄弟として育てられました」
「鉄笛を吹いていたな」
「ええ。旅の慰めに吹くよう、お供をしてきた方から、言われていましたので。
ほんとうは、俺は竹の笛を吹きます。自分でも、作りますから」
「見せてくれるか」
王清は、腰に差した鉄笛を見せたが、渡そうとはしなかった。
真中に、薄い鉄の板が張り付けてある。
鍛冶屋の仕事だろう。
「こういう鉄笛を、俺は知っているぞ。別の鉄笛もだ」
「馬麟様が、吹かれていたそうです。
もう一本は、張平殿のものでしょう」
「そうか」
山士奇は、王清のそばに腰を降ろした。
馬麟の鉄笛も、張平の鉄笛も、野営の地で聴いた。近くではない。
風に乗って流れてきたという感じだったが、妙に心に残る音色だったのだ。
「俺は、山士奇という」
王清は、ちょっとだけ頷いたように見えた。
「おまえの兄弟というのは、もしかすると王貴か?」
「そうです」
「なるほど。母親は、扈三娘殿」
「母は、違います。父が、王英といいます」
「名は知っている。
俺は梁山泊軍に加わったのが遅かったから、王英殿と会ったことはない。
扈三娘殿は知っているが」
「父の記憶はありません。
母が二人いると思えと、扈三娘殿には言われていました」
王清は、鉄笛を腰に差した。
「おまえが、なぜ、それを?」
「旅の途中で、気を鎮めるために、鉄笛の音が必要だ、と言われました。
御自信も、笛の名手であられるのですが」
旅の間、ずっと気が立っているということか、と山士奇は思った。
「おい」
声をかけられ、山士奇は思わず躰を固くした。
「おまえ、王清だな」
「はい、史進殿」
「燕青は、まだ出てこないのか?」
「まだです」
「眼が、見えるようになったというのは、ほんとうか?」
「真中だけが。
黒い布の真中に、明りの穴が開いたようになり、それからかたちも見えるようになったそうです。
それでも、そばで俺の顔が、なんとなくわかるぐらいです」
いきなり王清が跳躍した。
史進の拳が空を鳴らしたのに、しばらくして山士奇は気づいた。
近くの兵を、蹴りあげたり、殴りつけたりする、そんな拳とは、まるで違っていた。
当たれば、骨は砕けただろう。
「王進先生の稽古か。それとも、燕青のやうか?」
「お二人に、稽古をつけていただいていました。
王進先生とは、一刻だけ、むき合って立つだけです。
いまでは、倒れず無心に立っていられます」
「燕青とは?」
「はじめは、打ち倒せと言われました。
稽古を始めてひと月は、まったく動かれず、俺が打ち倒すだけでした」
(…この続きは本書にてどうぞ)
鉄笛だった。
その音色が、山士奇の心のどこかに、はっきりと残っていた。
吹いていた人間は二人だった、とシュウ聚義庁の階を降りながら、山士奇は思った。
馬麟と、張平である。
広場を歩いていくと、湧水のそばに、背中が一つ見えた。
ここの湧水は、周囲が水浸しになろうとなら枚と、同じように湧いては,賽外に流れだしている。
見知らぬ顔が、鉄笛を吹いていた。
山士気の気配がそうさせたのか、吹くのをやめ、顔をこちらにむけてきた。
「おまえは?」
「王清といいます。三刻ほど前に、ここに入りました。」
「梁山泊の人間か?」
そういう匂いはした。
しかし、兵ではない。
軍人が放つ、集団を感じる気配が、まるでないのだ。
「兄弟は、梁山泊の人間です。
兄、弟ではなく、双子の兄弟として育てられました」
「鉄笛を吹いていたな」
「ええ。旅の慰めに吹くよう、お供をしてきた方から、言われていましたので。
ほんとうは、俺は竹の笛を吹きます。自分でも、作りますから」
「見せてくれるか」
王清は、腰に差した鉄笛を見せたが、渡そうとはしなかった。
真中に、薄い鉄の板が張り付けてある。
鍛冶屋の仕事だろう。
「こういう鉄笛を、俺は知っているぞ。別の鉄笛もだ」
「馬麟様が、吹かれていたそうです。
もう一本は、張平殿のものでしょう」
「そうか」
山士奇は、王清のそばに腰を降ろした。
馬麟の鉄笛も、張平の鉄笛も、野営の地で聴いた。近くではない。
風に乗って流れてきたという感じだったが、妙に心に残る音色だったのだ。
「俺は、山士奇という」
王清は、ちょっとだけ頷いたように見えた。
「おまえの兄弟というのは、もしかすると王貴か?」
「そうです」
「なるほど。母親は、扈三娘殿」
「母は、違います。父が、王英といいます」
「名は知っている。
俺は梁山泊軍に加わったのが遅かったから、王英殿と会ったことはない。
扈三娘殿は知っているが」
「父の記憶はありません。
母が二人いると思えと、扈三娘殿には言われていました」
王清は、鉄笛を腰に差した。
「おまえが、なぜ、それを?」
「旅の途中で、気を鎮めるために、鉄笛の音が必要だ、と言われました。
御自信も、笛の名手であられるのですが」
旅の間、ずっと気が立っているということか、と山士奇は思った。
「おい」
声をかけられ、山士奇は思わず躰を固くした。
「おまえ、王清だな」
「はい、史進殿」
「燕青は、まだ出てこないのか?」
「まだです」
「眼が、見えるようになったというのは、ほんとうか?」
「真中だけが。
黒い布の真中に、明りの穴が開いたようになり、それからかたちも見えるようになったそうです。
それでも、そばで俺の顔が、なんとなくわかるぐらいです」
いきなり王清が跳躍した。
史進の拳が空を鳴らしたのに、しばらくして山士奇は気づいた。
近くの兵を、蹴りあげたり、殴りつけたりする、そんな拳とは、まるで違っていた。
当たれば、骨は砕けただろう。
「王進先生の稽古か。それとも、燕青のやうか?」
「お二人に、稽古をつけていただいていました。
王進先生とは、一刻だけ、むき合って立つだけです。
いまでは、倒れず無心に立っていられます」
「燕青とは?」
「はじめは、打ち倒せと言われました。
稽古を始めてひと月は、まったく動かれず、俺が打ち倒すだけでした」
(…この続きは本書にてどうぞ)
