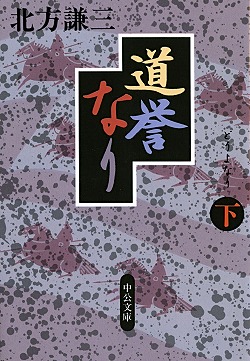
道誉なり 下
室町幕府の権力を二分する、足利尊氏・高師直派と尊氏の実弟直義派との抗争は、もはや避けられない情勢となった。
両派と南朝を睨みながら、利害を計算し離合集散する武将たち。
熾烈極まる骨肉の争いに、将軍尊氏はなぜ佐々木道誉を必要としたのか。
そして、道誉は人間尊氏に何を見ていたのか。
「ばさら太平記」堂々の完結!
室町幕府の権力を二分する、足利尊氏・高師直派と尊氏の実弟直義派との抗争は、もはや避けられない情勢となった。
両派と南朝を睨みながら、利害を計算し離合集散する武将たち。
熾烈極まる骨肉の争いに、将軍尊氏はなぜ佐々木道誉を必要としたのか。
そして、道誉は人間尊氏に何を見ていたのか。
「ばさら太平記」堂々の完結!
<文庫本>1999年 2月18日 初版発行
花一揆
暑い盛りだった。
一忠と阿曽がいた。
高橋屋の一室である。
阿曽は隻眼だったが、利く方の眼も小さく畳んだ晒を当てて塞いでいた。
次第に、視力が失せてきたのである。
このまま失明していくものと思われたが、阿曽の表情は暗くなかった。
「この世のいたましさを、この眼で見ないですみます」
阿曽は、道誉にそう言った。
ただ、猿楽の一座をそうするか、考えなければならなかった。
そこに、一忠が現れたのである。
「この際、近江だ大和だとこだわるのは、いたずらに芸域を狭いものにしてしまいはせぬかのう、阿曽」
「芸は、ただ芸でございます。ただ、ひとりひとりが受け継いできたものでございます」
阿曽の一座は大きくなって、いくつかに分かれた。
それぞれで生計を立ててはいるが、未熟なものだけを集めて、阿曽が連れていたのである。
「私が預かろうかな、阿曽殿。聞けば、まだ童ばかりだというではないか。阿曽殿がいやでなければ、この一忠の芸をその者たちに伝えたい」
「それは、望みようのないことです。ただ、一忠殿は、観世丸という童を抱えておられるではありませんか。それに、犬王もお世話になるかもしれません」
「あの二人は、それぞれに立つだろう。私はそう思う」
「あの二人を、もうお認めになっているのですね、一忠殿は」
「芸は生まれながらのものでもある。阿曽殿にはわかると思うが、そういう人間が、稀にいるものだ」
「まさしく、あの二人の童は」
こういう話が、道誉は好きだった。
芸は、人の心を揺り動かす。
この世にそういうものがなければ、人はただいたましいだけである。
特に、戦の多い時代はそうだ。
「よし、一忠に預かって貰おう。それでよいな、阿曽?」
阿曽は頭を下げた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
暑い盛りだった。
一忠と阿曽がいた。
高橋屋の一室である。
阿曽は隻眼だったが、利く方の眼も小さく畳んだ晒を当てて塞いでいた。
次第に、視力が失せてきたのである。
このまま失明していくものと思われたが、阿曽の表情は暗くなかった。
「この世のいたましさを、この眼で見ないですみます」
阿曽は、道誉にそう言った。
ただ、猿楽の一座をそうするか、考えなければならなかった。
そこに、一忠が現れたのである。
「この際、近江だ大和だとこだわるのは、いたずらに芸域を狭いものにしてしまいはせぬかのう、阿曽」
「芸は、ただ芸でございます。ただ、ひとりひとりが受け継いできたものでございます」
阿曽の一座は大きくなって、いくつかに分かれた。
それぞれで生計を立ててはいるが、未熟なものだけを集めて、阿曽が連れていたのである。
「私が預かろうかな、阿曽殿。聞けば、まだ童ばかりだというではないか。阿曽殿がいやでなければ、この一忠の芸をその者たちに伝えたい」
「それは、望みようのないことです。ただ、一忠殿は、観世丸という童を抱えておられるではありませんか。それに、犬王もお世話になるかもしれません」
「あの二人は、それぞれに立つだろう。私はそう思う」
「あの二人を、もうお認めになっているのですね、一忠殿は」
「芸は生まれながらのものでもある。阿曽殿にはわかると思うが、そういう人間が、稀にいるものだ」
「まさしく、あの二人の童は」
こういう話が、道誉は好きだった。
芸は、人の心を揺り動かす。
この世にそういうものがなければ、人はただいたましいだけである。
特に、戦の多い時代はそうだ。
「よし、一忠に預かって貰おう。それでよいな、阿曽?」
阿曽は頭を下げた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
