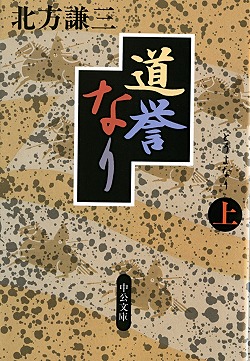
道誉なり 上
「毀すこと、それがばさら」
───六波羅探題を攻め滅ぼした足利高氏(尊氏)と、政事を自らつかさどる後醍醐帝との暗闘が風雲急を告げる中、「ばさら大名」佐々木道誉は数々の狼籍を働きながら、時代を、そして尊氏の心中を読んでいた。
帝が二人立つ混迷の世で、尊氏の天下獲りを支え、しかし決して同心を口にしなかった道誉が、毀そうとしたものとは・・・。
渾身の歴史巨編。
「毀すこと、それがばさら」
───六波羅探題を攻め滅ぼした足利高氏(尊氏)と、政事を自らつかさどる後醍醐帝との暗闘が風雲急を告げる中、「ばさら大名」佐々木道誉は数々の狼籍を働きながら、時代を、そして尊氏の心中を読んでいた。
帝が二人立つ混迷の世で、尊氏の天下獲りを支え、しかし決して同心を口にしなかった道誉が、毀そうとしたものとは・・・。
渾身の歴史巨編。
<文庫本>1999年 2月18日 初版発行
激流
陣幕の外で、酔った声があがった。
兵たちに、それほどの酒は与えていない。
それでも、戦陣である。
わずかな酒でも、気持が昂るようだ。
陣幕を幾重にも張りめぐらし、旗で飾り立てた本陣だった。
道誉は、ひとりで床几に腰を降ろしていた。
酒はない。
兵糧さえ口にしていなかった。
柏原城の一里ほど西に、本陣は置いていた。
柏原城が、詰めの城となる。
城に一千、本陣に二千の兵力を分けた。
城の一千は眠ることさえせず、常に敵に備えている。
一日ずつ、本陣の兵と交替させるのだ。
「蜂助です」
声がかかった時は、蜂助はすでに道誉の前で片膝をついていた。
陣幕の動きに、道誉は気づかなかった。
「五辻宮は、興奮しておられます。集まってくる野伏せりはおよそ四千。血に飢えております。落武者になれば、誰彼の区別なく打ちかかろうという構えで。姫橋殿でも、押えきれますまい」
姫橋には、仕事があった。
それだけうまくやってくれればいい。
六波羅は壊滅したといっても、鎌倉はまだある。
幕府軍に正面切って挑む時期にはまだ早いかもしれない、と道誉は思っていた。
この地に陣を張っていれば、どういう理由をつけることもできる。
「殿軍の本隊が、追いつくことはあるまいな」
「もう、京へ返しているところです。そのまま降参ということになりましょう」
南北の六波羅探題は、京を捨てていた。
時益は逃亡の途中で射殺され、いまは仲時が一族郎党数百と近江に逃げ込んでいた。
面倒なのは、持明院統の天子、上皇を連れていることである。
大覚寺の後醍醐帝は、伯耆船上山にあった。
時代の動きが、速かった。
拠って立つ場所は、いまのところどこにもない。
六波羅が陥ちたと言っても、金剛山を囲んでいる数万の幕軍はまだいた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
陣幕の外で、酔った声があがった。
兵たちに、それほどの酒は与えていない。
それでも、戦陣である。
わずかな酒でも、気持が昂るようだ。
陣幕を幾重にも張りめぐらし、旗で飾り立てた本陣だった。
道誉は、ひとりで床几に腰を降ろしていた。
酒はない。
兵糧さえ口にしていなかった。
柏原城の一里ほど西に、本陣は置いていた。
柏原城が、詰めの城となる。
城に一千、本陣に二千の兵力を分けた。
城の一千は眠ることさえせず、常に敵に備えている。
一日ずつ、本陣の兵と交替させるのだ。
「蜂助です」
声がかかった時は、蜂助はすでに道誉の前で片膝をついていた。
陣幕の動きに、道誉は気づかなかった。
「五辻宮は、興奮しておられます。集まってくる野伏せりはおよそ四千。血に飢えております。落武者になれば、誰彼の区別なく打ちかかろうという構えで。姫橋殿でも、押えきれますまい」
姫橋には、仕事があった。
それだけうまくやってくれればいい。
六波羅は壊滅したといっても、鎌倉はまだある。
幕府軍に正面切って挑む時期にはまだ早いかもしれない、と道誉は思っていた。
この地に陣を張っていれば、どういう理由をつけることもできる。
「殿軍の本隊が、追いつくことはあるまいな」
「もう、京へ返しているところです。そのまま降参ということになりましょう」
南北の六波羅探題は、京を捨てていた。
時益は逃亡の途中で射殺され、いまは仲時が一族郎党数百と近江に逃げ込んでいた。
面倒なのは、持明院統の天子、上皇を連れていることである。
大覚寺の後醍醐帝は、伯耆船上山にあった。
時代の動きが、速かった。
拠って立つ場所は、いまのところどこにもない。
六波羅が陥ちたと言っても、金剛山を囲んでいる数万の幕軍はまだいた。
(…この続きは本書にてどうぞ)
